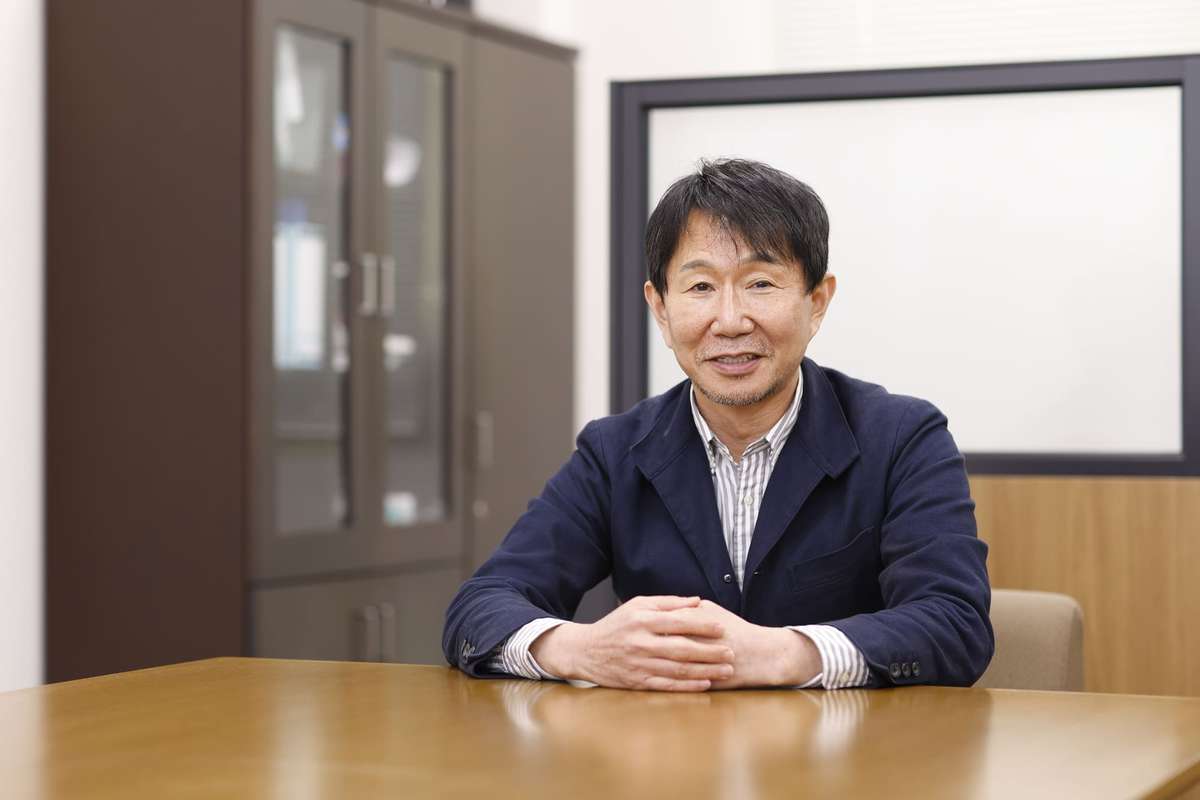データサイエンス系の人材が不足することはわかっていた
――日本で最初にデータサイエンス学部を創設したのが滋賀大学です。経緯や狙いを教えてください。
椎名氏:データサイエンス系の人材が不足することは、政府の座談会や審議会でも議論されていました。データサイエンスは学問的には、情報学と統計学から成り立っています。私は統計学が専門ですが、実は日本の大学には統計学部がないのです。欧米にはた�くさんあるのに、日本はこのままでいいのだろうかということが根底にありました。
もう一つ、滋賀大学の固有の課題もありました。当時、滋賀大学は教育学部と経済学部の2学部で構成されていました。国立大学に文系学部は不要といった議論もあり、滋賀大学にも危機感がありました。当時の佐和隆光学長は経済学が専門で、中でも計量経済学の第一人者でした。新学部の設立に当たって、統計を使った学部が良いのではと音頭を取られたようです。
――そして、データサイエンス学部ができたのですね。
椎名氏:統計出身の教員も多いですから、統計学部という名称にする方法もあったでしょう。でも、幅広くデータを扱う学問としての「データサイエンス」を学部の名称にしました。データ分析、データアナリティクスの道具として統計は重要です。しかし、データを集め、課題を見つけるといった前後のプロセスも含めると、幅広い意味でのデータサイエンスを扱うことにしたのは良かったのではないかと思っています。
分析したところで、相手に「は、それで?」と言われたら終わり。データサイエンスには文系の力が必要
――日本で最初のデータサイエンス学部として「文理融合」を掲げています。
椎名氏:データサイエンス学部では文理融合の学問をうたい、文系の人も怖がらずに来てくださいとメッセージを伝えてきました。そうした取り組みにより、初年度の入学生は4割ぐらいが文系出身でした。文系と理系の出身者が混じり合ってコラボレーションしてほしいという狙いに合致したのです。
ところが、最近は文系出身者が3��割を切るようになって、少し問題だと感じています。入試の数学は文系でも学ぶ範囲から主に出題していますし、大学のパンフレットも文系出身者の学生を紹介してアピールしています。それでも文系出身者が減っている理由の1つはSNSなどの情報でしょう。在学生の「数学を鍛えられる」「苦労する」と書かれている投稿を読むと、受験生が躊躇してしまうようです。文理融合の良い点を生かすためにも、文系出身者の確保は課題です。
――文系の学生にこだわる理由は?
椎名氏:そもそもデータサイエンスが何かということを考えてみます。データサイエンスには、狭義のデータサイエンスと広義のデータサイエンスがあります。一般にデータサイエンスと呼ばれるのは、狭義のものです。この中には、「データ収集・加工・処理」「データ分析・解析」「価値の発見・創造」といったプロセスが含まれます。最初のデータ収集・加工・処理は情報学、真ん中のデータ分析・解析は統計学の範疇で、いわゆる理系の学問です。ところが、データを集めて、分析したところで、相手に「は、それで?」と言われたら終わりなんです。分析、解析した中から、価値を発見したり創造したりしなければいけません。

工場なら不良品率を減らす、Eコマースなら売上を上げるといった目的があります。�価値は「人間を幸せにする何か」と定義でき、価値の発見や創造に結びつかないといくらデータをいじってもだめなのです。目的は価値の発見や創造であり、情報学や統計学が対象とする分野はそのための手段だと授業でも強調しています。価値を見出すとなると、人間の理解が必要になります。そこでは文系的な要素がとても重要です。文系の人がいると、実際にゼミでも面白いアイデアが出てきます。こうした文理融合の価値を高めていくためにも、文系の学生が必要なのです。
専門領域と課題解決の双方を行き来しながら、価値の創造を学ぶ
――データサイエンス学部で、価値の発見や創造を学ぶために取り組んでいることは。
椎名氏:価値の発見・創造を学生に教えるのはとても難しいことです。ある種の課題感や、現状を変えたいという希望を、実社会に生きていない学生は持ち合わせていないからです。そのため、企業や地方公共団体と連携して、民間や市町村で実際にどのような課題や希望があるかを話してもらい、匿名化した実データも提供してもらって、それらを課題にした演習を実施しています。
――演習は学年が進んでからの取り組みですか。
椎名氏:いいえ、1年生からです。1年生は情報学や統計学の勉強を始めたばかりですから大した分析はできませんが、何らかの課題をデータで解くことを身に着けていきます。3年生、4年生になると、データ収集や分析のレベルが高くなり、「企業から面白い発見だね」と評価され、実際に課題解決に使ってもらうような価値の発見につながることもあります。世の中にはデータサイエン��スを学ぶための例題も多くありますが、生の課題と実際のデータに触れられることは学生のモチベーションにつながっていますし、未解決の問題を解けたときには大きな喜びを感じているようです。

データサイエンス学部での学びは、どうしても情報学や統計学などの「ツール」に相当する専門領域を低学年でたくさん学習して、その後に個別の課題に対応することになりがちです。すると課題への対応の時間が限られてしまいます。企業や自治体と連携した演習を1年生から実施することで、専門領域と課題解決の双方を行き来しながら学習を進めるスパイラル型の理想に少しでも近づけられるようにしています。
――卒業後はどのような道に進んでいますか。
椎名氏:入学するときは、道具としてのデータサイエンスを極めたいと考えている学生が多いようですが、実際に就職したときにデータサイエンティストになるかというと、そうでもありません。総合職として、人事でも営業でも、データサイエンスを勉強した強みを生かしたいと考えた就職も多いようです。ガチなデータサイエンティストになるのではなく、データサイエンスという得意技を使ってゼネラリストとして会社に貢献する方向性です。
日本に、データに基づく判断をする文化を醸成したい
――滋賀大学をはじめとした大学でデータサイエンス学部などが増えていくことで、社会に及ぼす影響をどう考えていますか。
椎名氏:日本では、何かを判断したり説得したりするときに、データに基づくという文化がまだ育っていなくて、顔色を見て判断するようなところがあります。データサイエンス学部の卒業生は、データを武器にしてプレゼンや説得をできるような訓練をされています。データで語ると説得力があると認知されるような文化を育むことが一つの目標です。

データに基づいて議論して選択をした場合、失敗したとしても、「予測が失敗した」「想定外のことが起きた」といった失敗の理由を見つけることができます。しかし日本流の顔色やパワーバランスで選択した場合には、明確な理由を求めることができず、不満の蓄積や責任のなすりつけ合いが生じます。データに基づいて議論する文化は社会の変革につながると感じています。
――企業や自治体などとの連携による変化は。
椎名氏:外部との連携は、最近では年間100社・団体にも上り、延べ300社・団体に協力を得ています。教員だけでなく、院生や学部生を巻き込んで企業などの課題を解いていく機会が多くあることは、滋賀大学のデータサイエンス学部で学ぶメリットです。学部から�大学院へは100人のうち10名以上が進学しています。他大学に進学する学生も少なくありません。それだけでなく、定員40名の大学院は社会人を中心に倍率が2倍にのぼるほど人気です。社会人大学院生は、企業や団体で抱えている生の課題やデータを持ってきて、2年間で修士論文にしていきます。こうした社会人大学院生と、学部生、大学院生が交流することで、社会人の課題の立て方を学んだり、リスキリングの必要性を感じたりする良い効果が現れています。
――データサイエンスを活用する上で、話題のAIと人間の役割はどのようになっていくでしょう。
椎名氏:いくらChatGPTがうまく文章を作っても、「課題の発見・設定」はAIにはまだできませんし、データサイエンスが導き出した結果からリアルの世界に「実装・業務改善」することは人間だけしかできません。さらに、実際に会社や社会で動かして改善をするとなると一人ではできないので、他者を動かすためのプレゼンテーションやコミュニケーションの能力が求められます。狭義のデータサイエンスではAIも活躍していくでしょうが、その前後に広がる広義のデータサイエンスによる価値創造は人間にしかできないことです。データサイエンス学部の文理融合の教育で、そうした学びを高めてもらいたいと考えています。
文/岩元 直久