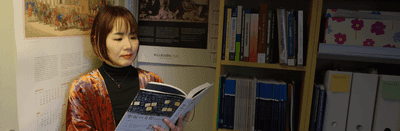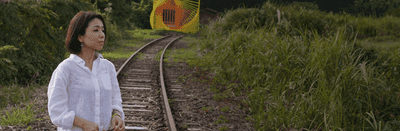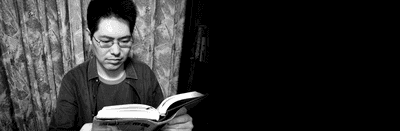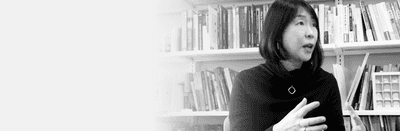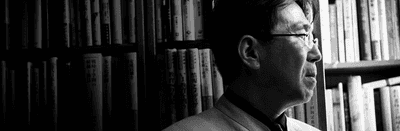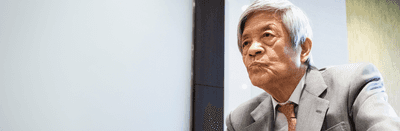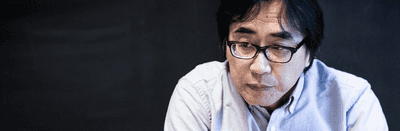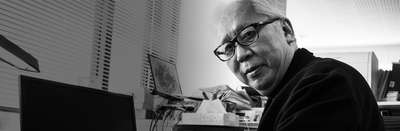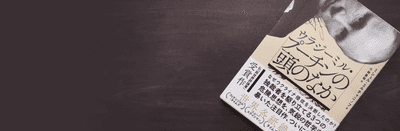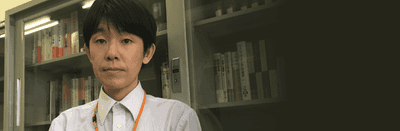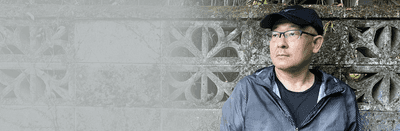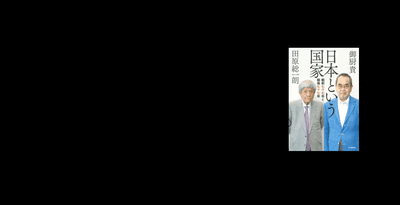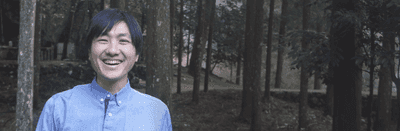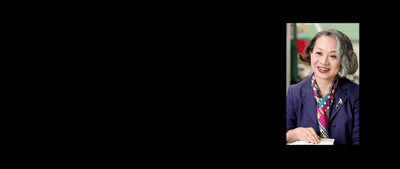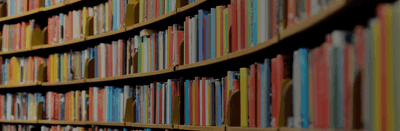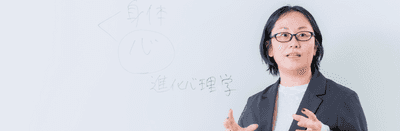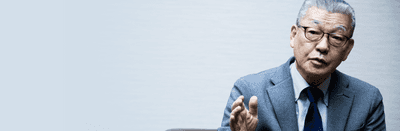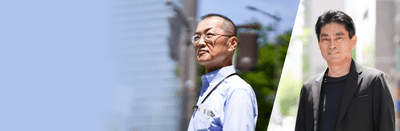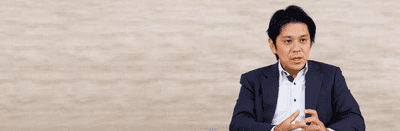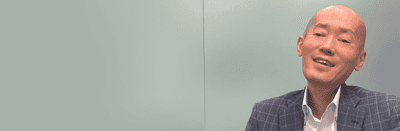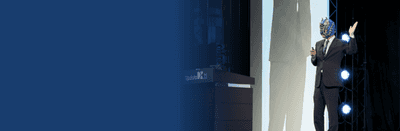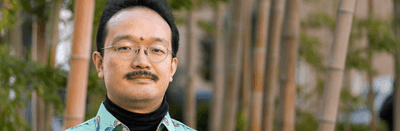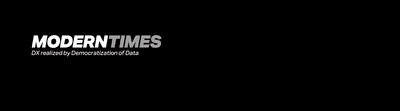著者一覧
![饗庭伸]()
饗庭伸
![今井明子]()
今井明子
![井山弘幸]()
井山弘幸
![大川祥子]()
大川祥子
![大場紀章]()
大場紀章
![暮沢剛巳]()
暮沢剛巳
![小松原織香]()
小松原織香
![小松由佳]()
小松由佳
![佐々木賢一]()
佐々木賢一
![田口勉]()
田口勉
![高水裕一]()
高水裕一
![久野愛]()
久野愛
![山﨑広子]()
山﨑広子
![岡村 毅]()
岡村 毅
![Modern Times編集部]()
Modern Times編集部
![新田浩之]()
新田浩之
![野原佳代子]()
野原佳代子
![広井良典]()
広井良典
![DXで未来を拓く 先駆者たちの現在地]()
DXで未来を拓く 先駆者たちの現在地
![小二田誠二]()
小二田誠二
![佐々木隆仁]()
佐々木隆仁
![佐藤 卓己]()
佐藤 卓己
![佐藤秀明]()
佐藤秀明
![柴田重信]()
柴田重信
![島薗進]()
島薗進
![髙橋 信久]()
髙橋 信久
![田原総一朗]()
田原�総一朗
![玉木俊明]()
玉木俊明
![仲俣暁生]()
仲俣暁生
![中村航]()
中村航
![長坂俊成]()
長坂俊成
![畑中章宏]()
畑中章宏
![福島真人]()
福島真人
![藤田盟児]()
藤田盟児
![松浦晋也]()
松浦晋也
![松村秀一]()
松村秀一
![村上陽一郎]()
村上陽一郎
![村山司]()
村山司
![村山哲也]()
村山哲也
![ミシェル・エルチャニノフ]()
ミシェル・エルチャニノフ
![Web3.0は男の顔をしていない]()
Web3.0は男の顔をしていない
![瀬谷ルミ子]()
瀬谷ルミ子
![Jonathan Gottschall]()
Jonathan Gottschall
![村上貴弘]()
村上貴弘
![安岡宏和]()
安岡宏和
![岡西政典]()
岡西政典
![窪田薫]()
窪田薫
![島村修平]()
島村修平
![お知らせ]()
お知らせ
![長滝 祥司]()
長滝 祥司
![御厨貴]()
御厨貴
![特集]()
特集
![青木真兵]()
青木真兵
![鈴木貞美]()
鈴木貞美
![藤垣 裕子]()
藤垣 裕子
![橋口慎一]()
橋口慎一
![本棚演算]()
本棚演算
![森本 裕子]()
森本 裕子
![データサイエンティストと歩む]()
データサイエンティストと歩む
![イベント開催]()
イベント開催
![Kaede]()
Kaede
![池上高志]()
池上高志
![井上顧基]()
井上顧基
![佐藤一雅]()
佐藤一雅
![田口善弘]()
田口善弘
![中根佑子]()
中根佑子
![細野昭雄]()
細野昭雄
![中村健太郎]()
中村健太郎
![野口諒子]()
野口諒子
![薄井研二]()
薄井研二
![芙和せら]()
芙和せら
![日本製薬工業協会]()
日本製薬工業協会
![橋田浩一]()
橋田浩一
![有本真由]()
有本真由
![木村守宏]()
木村守宏
![澁谷紳一郎]()
澁谷紳一郎
![佐々木賢一・山崎政直]()
佐々木賢一・山崎政直
![田中亮宇]()
田中亮宇
![大澤夏美]()
大澤夏美
![町田英之]()
町田英之
![木村知司]()
木村知司
![太田雅一]()
太田雅一
![小宮裕和]()
小宮裕和
![マスクド・アナライズ]()
マスクド・アナライズ
![矢沢陽介]()
矢沢陽介
![杉山達朗]()
杉山達朗
![中津 繁]()
中津 繁
![佐伯 真二郎]()
佐伯 真二郎
![Modern Times トレンドやや深堀り]()
Modern Times トレンドやや深堀り
![鈴木誠之]()
鈴木誠之
![村上 知久]()
村上 知久