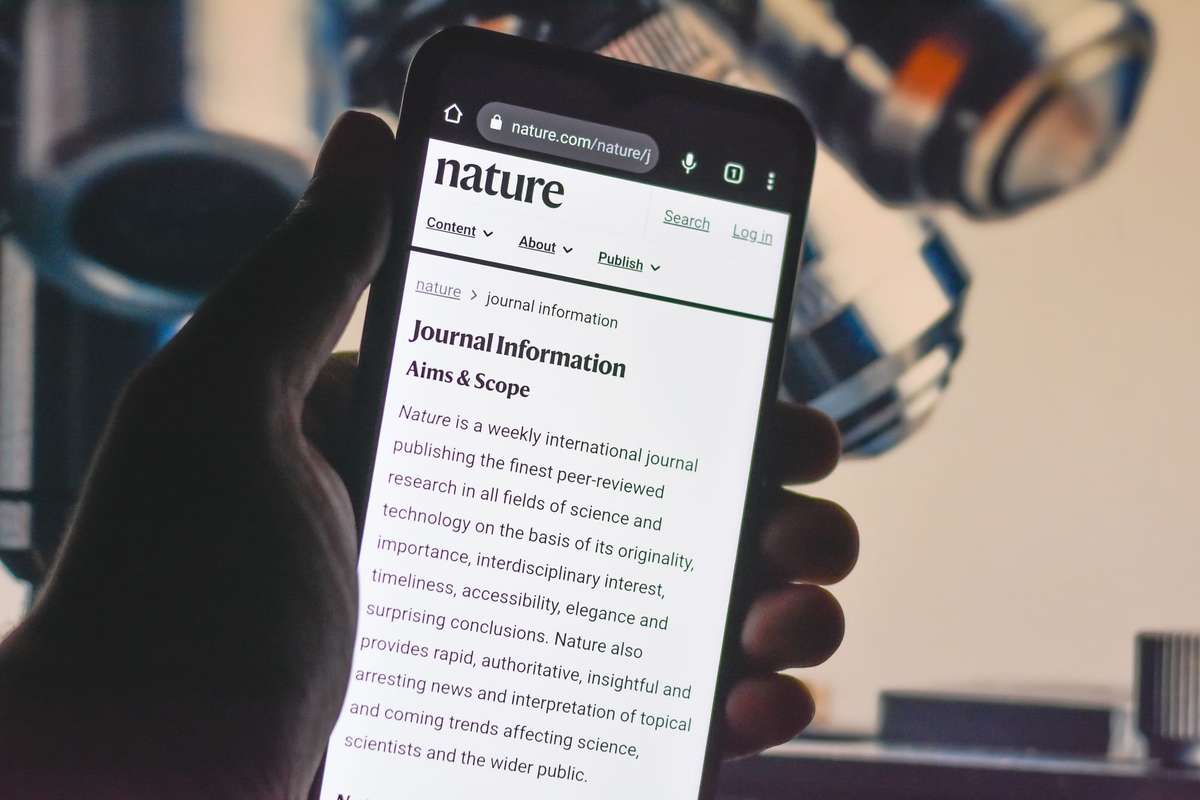科学者とは、本を書く人?
だいぶ前、大学の少人数授業の際、理系とはあまり縁がなさそうな学生達に対して、科学者というのは一言でいうと何をする人か、という質問をしたことがある。色々な回答があったが、唯一覚えているのが、科学者とは「本を書く人」という回答であった。ボイル(R.Boyle)やダーウィン(C.Darwin)の時代ならその定義��も全く間違いとはいえないが、これは現在では当てはまらない回答である。
勿論、科学者にも(様々なタイプの)本を書く人はいて、教科書や入門書、あるいはそれ以外の評論等を書いて、ものによってはベストセラーになり、なんとか賞をとってメディアの寵児になる場合もある。しかし正解は、科学者が書くのは、論文、しかも専門誌に掲載されたそれである。
論文とは、ある意味、科学的実践の最重要インフラの一つとでも言える制度である。それゆえ科学技術社会学(STS)では、その役割について突っ込んだ議論をしてきた。実際ラトゥール(B.Latour)のような論者は、科学の性質を論じる際、仰々しい哲学的認識論よりも、むしろ論文という小さなメディアが持つ重要性を強調している。つまりこの媒体は、色々な場所に持ち運び可能である(mobile)と同時に、場所が変わってもその内容が変化しない(immutable)という点に、科学的実践の一つの根拠を見ているのである。
理系、そして近年では人文社会系でも、論文をいかに良いジャーナルに載せるか、という競争が激しくなってきている。勿論ジャーナルが高名であればあるほど、その道は険しい。掲載のためには同業者によるチェックが入り、そこを通過しないと論文は掲載されない。それがいわゆるピア・レビュー、あるいは査読という仕組みである。雑誌の方針によって、査読者の数、名前を公表するかしないか(ダブルブラインドは著者、査読者ともに匿名、シングルブラインドは査読者のみ匿名)等色々なバリエーションがある。
PCRはジャーナルの査読に落ちている
科学研究費の申請書には、査読つき論文か否か、という弁別があるが、査読つき論文の方がより高い品質保証があるという意味である。査読つき論文中心主義は、もともと理系の慣習だったが、人文社会系にもその波が押し寄せており、英国では社会科学系も、著作よりも査読つき論文数が業績の基礎になりつつある。だがこうした波には弊害もある。
査読によって拒否された論文がその後ノーベル賞をとったという事例はいくつもあるが、コロナ禍でも活躍したPCRはその典型である。国内の例でいえば、前に戦後最大のバイオ研究計画である「タンパク3000」プロジェクトについて調べていた時に、その立役者の一人の講演会を聞きに言った際の話がある。彼がいうには、論文を投稿するということは、4割だか6割だかいるバカな[ママ]査読者との戦いだという。彼は当時としては極めて先駆的だった高速度ゲノム解析の案を愚弄した覆面査読者に非常に腹を立て、その文言をどこかの国際的アーカイブに永久保存しているらしい。
査読者の先見性の無さという話は、何も理系には限らない。STS周辺でも、インフラ研究で有名なある知り合いは、自分が書いた論文への査読報告に応じて渋々修正したが、後に担当した別の査読者が彼に直接「書き直す前の方がよかった」と言ったという。
STSのような学際的分野では、適切な査読者を見つけるのも一苦労らしいが、結果としてとんでもないコメントがつく場合も少なくない。Science as Cultureという、STSでは中程度のランクの雑誌に投稿した際、一人の査読者が明らかに論文の趣旨を誤解しており、やたらとグラフィティ論を読めと迫ってきた。他の査読者の肯定的なコメントとはだいぶ異なる要求で、スルーせざるを得なかったが、編集部も混乱の極みで、以前に書いてよこしたコメントを覚えていないようだった。最後に別の新査読者の妨害にあい、結局掲載拒否になったが、すぐ部分的に書き直して、同程度の別の雑誌に送ったらあっというまに受理されたのも驚きであった。
査読論文中心主義の弊害
査読をめぐる混乱は、科学を超えて周辺分野にも及んでいる。その一つの問題が査読の長期化である。STS界隈で話題になったのはノルウェーの研究者の例で、論文を投稿してから4年以上も待たされ、挙げ句の果てに掲載拒否されたという話である。怒った著者が学界のニューズレターに苦情を投稿したのだが、編集者の弁明はいくつかあった。曰く、投稿される原稿の量の加速的増加、曰く、学際領域であるSTSにおいて、テーマと関係する査読者を見つけることの難しさ、更に一部の著名研究者に依頼が集中することによる遅滞等。このネタは研究者間では切実に受け止められるため、仲間うちでこの話題を出すと、オレは5年待った、いや7年だといった「武勇伝」が語られることもある。
勿論、こうした傾向はSTS誌に限られることではない。理系のみならず、社会科学系においても、この査読論文中心主義は益々強まる傾向があり、学界での評判の高いジャーナルへまず投稿、という傾向に近年拍車が掛かっていると聞く。原稿を完成したら、まずトップジャーナルに投稿し、駄目ならランクを�少しずつ落としていくという戦略である。英国の最古参の社会学雑誌の国際編集委員を手伝っていた時、しばしば編集部で話題になったのが、この「肝試し投稿」とでもいうべき悪しき慣習である。結局、殺到する原稿に対し、こうしたやり方での投稿をするな、という警告が雑誌のホームページに載ることになった。
投稿が殺到し、査読時間も長期化する傾向があるため、雑誌側も様々な手段を通じて査読に係わる負担を減らそうとする。その一つが英語でいうdesk rejectで、平たくいえば、投稿の入り口の部分ですぐ掲載拒否してしまうというやり方である。知り合いの学生が、英国誌に投稿を試みた時に、殆ど半時間で掲載拒否の連絡が来たといって驚いていた。よくよく聞けば、その雑誌は量的調査を中心とした雑誌で、彼の原稿は質的研究だったから、最初からカテゴリー違いだったのではあるが。
こうした攻防に加え、覆面査読者によるあまり好ましくない行為の噂は文理に係わらずよく耳にする。アメリカのラボでの研鑽経験がある生物学者達の話を聞いた際に、彼らが見聞したのは、査読側がライバル研究者の投稿を読み、その内容に応じて査読側が時間稼ぎをして自分のラボの研究を促し、他方投稿者は掲載拒否にしてしまったというあくどい振る舞いである。天然物化学系でも、投稿による情報の漏れ、悪用の事例があるといい、それを警戒して日本語で成果を発表するといった議論も聞いたことがある。
革新的な研究にはハンデがあることも
ピア・レビューという概念は、同じ分野の他の研究者(つまりピア)によって内容をチェ�ックすることで、論文の品質を保証するという趣旨に基づく。しかしその分野が学際的な場合、何をもってピアを定義するかはかなり難しい問題である。二つの領域の中間的な研究は、その両端からみると何となく不十分なものに見えることもある。学際研究は声高に称揚されるものの、査読者は片方に偏っている場合も多く、革新的な研究にはしばしばハンデがある。多くの領域にまたがるなんとか賞といった場合、各審査員がカバー出来る範囲が限られており、その守備範囲の間の、いわば無人地帯に落ち込んだ研究は日の目が当たらないのである。
また該当分野が論争で分裂している場合、その片方に依拠する論文は、反対側の立場の査読者にとっては論敵でもある。こうした状況は社会科学ではよくある話である。だいぶ前に、ある研究者が記号論的なテーマの本を英語で出版したかったが、査読者の一人がマルクス主義者で、端からそのアプローチを否定され出版に至らなかったという話を聞いたことがある。
先程登場した半時間で掲載拒否の学生は、今度は別の英語雑誌に投稿したが、この雑誌はSTSのある潮流(アクターネットワーク理論)を信奉しており、編集部から、掲載されたければこの学派の誰々を引用せよ、という圧力が掛かったという。本人は特にこの理論のシンパでも無かったが、論文を掲載させたかったので「魂を売った」そうである。前述した私の事例でも最終的に掲載を妨害してきたのは、北欧系の似たような立場の研究者であったようだ。
論文の行く末を左右する、査読者ガチャ
こうした査読をめぐる水面下の面倒臭い暗闘が��表面化して大問題になったのが、クライメート・ゲートという、地球温暖化問題に関する論文をめぐる内部メールが流出した事件である。温暖化懐疑派の投稿に対する、著名研究者グループの内輪のやりとりが漏れたもので、懐疑派にとっては温暖化論批判のための大きなネタとなったものである。しかし内容をみると、温暖化論者がデータを改竄したといった話ではなく(実際後の調査では、そうした不正は無かったとされている)、むしろ論争相手の議論を如何に封じ込めるかという、論文掲載をめぐるあれこれの政治的やりとりの一部が漏れたものであった。
このように、査読をめぐるゴタゴタは、気が重くなるものが少なくない。ただし、最後に付け加えると、こうした醜聞の一方で、たまに驚く程建設的なコメントをくれる査読者がいるというのも事実である。その結果論文の出来がかなり向上した。最近の流行り言葉でいえば、親ガチャならぬ査読者ガチャという風情すらある。そして親と同様査読者も殆ど(全くではないが)こちらの意思では決められない点も似ている。科学社会学者ペリー(S.Perry)の本のタイトルではないが、まさに『科学の人間的性質』のめんどくさい側面なのである。
参考文献
『真理の工場ー科学技術の社会的研究』福島真人(東京大学出版会 2017年)
『ゲノム敗北-知財立国日本が危ない!』岸宣仁(ダイヤモンド社 2004年)
『地球温暖化スキャンダル―2009年秋クライメートゲート事件の激震』スティーブン・モシャー, トマス・フラー 渡辺正訳(日本評論社 2010年)
Masato Fukushima(2020) Before Laboratory Life: Perry, Sullivan and the missed encounter between psychoanalysis and STS, BioSocieties15(2):271–293.
Masato Fukushima(2021)Noises in the Landscape: Disputing the Visibility of Mundane Technological Objects, Journal of Material Culture 24(1):64-84.
Bruno Latour (1987) Science in Action : How to Follow Scientists and Engineers through Society, Harvard University Press.
Stewart Perry (1966) The Human Nature of Science: Researchers at Work in Psychiatry. The Free Press.