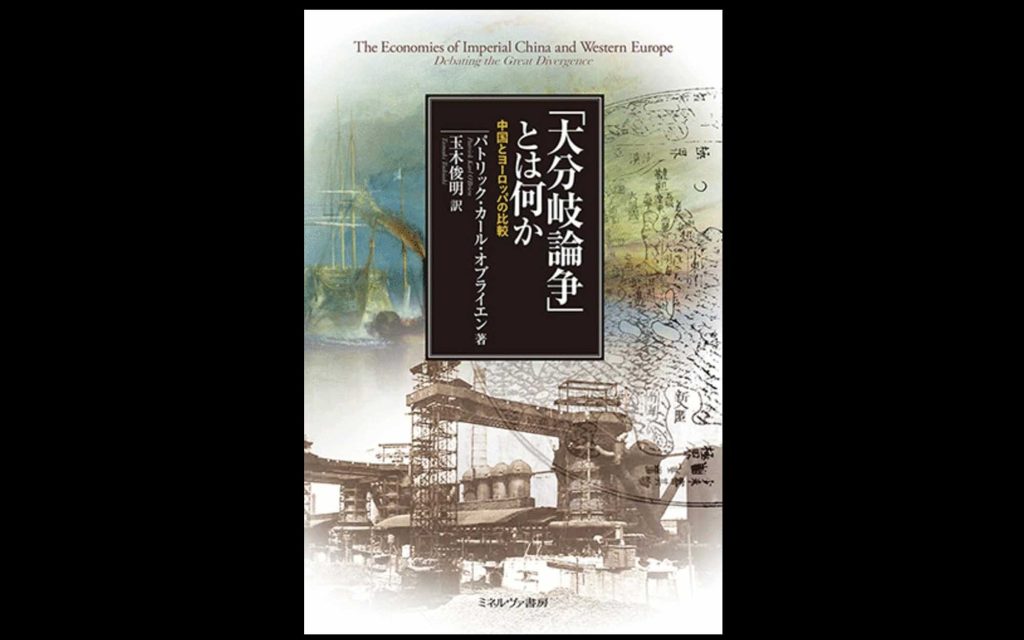世界中の歴史家に大きな影響を与えたケネス・ポメランツの『大分岐』
20世紀最後の年となった2000年、アメリカ人の中国史研究者ケネス・ポメランツがGreat Divergence(川北稔監訳『大分岐――中国、ヨーロッパ、そして近代世界経済の形成』名古屋大学出版会、2015年)を出版した。同書は、世界の経済史研究のあり方を根底的に変えることになった。中国の経済力が上昇しつつあった当時、歴史上、世界経済における中国経済の力が非常に強かった時代があったはずだと、人々に思い起こさせたのである。
この本の特徴は、ヨーロッパ、とくにイギリスと中国を比較して、1750年頃まではどちらも手工業にもとづく経済成長を経験していたのに対し、以降はヨーロッパが産業革命に成功したために、決定的な差がついたという点にある。
中国もヨーロッパも人口が増大したことに起因する経済的危機に見舞われた。そのなかでイギリス国内に大量に埋蔵されていたエネルギーとしての石炭と、新世界の広大な土地を活用によって経済は大きく発展し、産業革命が生じたというのである。ヨーロッパと中国は、このときに分岐することになった。ヨーロッパの経済的覇権を産業革命に求める視点は決して新しいものではないが、中国とヨーロッパが同様な経済成長を経験していたという考え方は、欧米人にとっては目新しいものであった。
ポメランツの議論は世界中の歴史家にまさに大きな影響を与えた。現在もなお、世界中で大分岐に関する議論は活発におこなわれているのである。ポメランツの影響は、若い世代にもおよんでいる。もはや私が親しいヨーロッパ��人の若手研究者は「アジア的生産様式」という表現を用い、アジアには進歩がないといったカール・マルクスとは異なり、ヨーロッパの方がずっと経済水準が高かったとは思ってはいない。むしろヨーロッパは、アジアよりも貧しかったのであり、近世(1500〜1800年)のどこかの時点でヨーロッパがアジアの経済水準を上回ったと考えている。しかも、ヨーロッパは、アジアの富をうまく理由して豊かになったと思っているヨーロッパ人研究者も少なくはない。歴史学研究の手法は、ドラスチックに変化した。
ポメランツの主張に賛成するにしろ反対するにせよ、『大分岐』こそ、現在の世界中の歴史家が意識しなければならない作品である。欧米人は、ヨーロッパ中心史観から抜け出そうとしており、それをもっとも端的にあらわした作品こそ、『大分岐』だからだ。
西洋でも日本でも、歴史研究の潮流は、大きく変化した。昭和末期に学生生活を送り、国民国家形成こそ歴史の進歩だと無邪気に信じていた私が習っていた歴史学は、もう遠い過去のものになってしまったようである。
1750年頃まで、ヨーロッパと東アジアの経済発展に大きな差はなかった
超長期的に見れば、ヨーロッパよりも中国の経済水準の方が高かったことは間違いない。ヨーロッパの優位は、この2〜3世紀間、どんなに長く見積もっても、5世紀はさかのぼらないことがわたるようになった。
ポメランツの『大分岐』については、グローバルヒストリアンの秋田茂が、次のように的確にまとめている。
本書の論点は2つある。その1つは、18世紀の半ば1750年頃まで、西欧と東アジアの経済発展の度合いにはほとんど差がなく「驚くほど似ていた、ひとつの世界」であったことを明らかにした。旧世界に散在した4つの中核地域――中国の長江デルタ、日本の畿内・関東、西欧のイギリスとオランダ、北インド――では、比較的自由な市場、広範な分業による手工業の展開(プロト工業化の進展)、高度に商業化された農業の発展を特徴とする「スミス的成長」が共通に見られた。資本蓄積のみならず、ミクロな指標として1人当たりカロリー摂取量、日常生活での砂糖や綿布消費量や出生率でも、これら4地域では差がなかった。比較対象として、中国全土でなく、最も経済が発展し人口密度も高かった長江デルタと西欧(現在のEU圏)に着目した点がユニークである。
第2は、ユーラシア大陸において発達した市場経済が、18世紀後半の人口増加に伴う生態環境の制約(エネルギー源としての森林資源の縮小や土壌流出など)に直面する中で、西欧だけがその危機を突破した原因を解明する。食糧・繊維(衣服)・燃料・建築用材のいずれを増産するにも、土地の制約に直面するなかで、イギリス(西欧)のみが、身近にあったエネルギーとしての石炭と、新大陸アメリカの広大な土地の活用によって、産業革命につながる社会経済の変革を実現できた。石炭と新大陸という全く偶然的な「幸運」があって初めて、西欧の台頭と工業化は可能になったのである(秋田茂「日本経済新聞」朝刊2015年7月19日付。ここでは、https://www.nikkei.com/article/DGXKZO89488490Y5A710C1MY7001/)。
単純にいうなら、長期間にわたり、西欧と中国は手工業にもとづく(スミス的)経済成長を実現していたが、西欧、とくにイギリスは、大西洋経済の開発と石炭の利用により、圧倒的に大きな経済成長を実現したというわけである。
中国経済史に詳しいオブライエンが『大分岐』に新たな視点を提示する
『大分岐』が上梓されて20年以上がすぎ、いまや「大分岐論」そのものが、一つの歴史となった。そのタイミングで出版された、パトリック・カール・オブライエン著(玉木俊明訳)『大分岐論争とは何か――中国とヨーロッパの比較』(ミネルヴァ書房、2023年。原著は2020年)は、ポメランツの研究史をまとめ、さらにオリジナルな視点を提示した本である。本書は博識で知られるパトリック・オブライエンが、カリフォルニア学派との対話を中心として「大分岐論」に関する新たな視点を提示した。
オブライエンは世界最高水準のグローバル経済史家であり、ポメランツの友人である。さらにケント・デングという中国経済史の重鎮と、いくつもの共同論文を発表してきた。したがって、中国経済史についてもかなりレベルの高い知識をもっているはずである。
オブライエンの研究の特徴は、「比較史」にある。しかもポメランツによれば、オブライエンの比較史は、おそらく無意識のうちに、『大分岐』の執筆に大きな影響を与えた。とすれば本書は、オブライエンの�影響を受けたポメランツが書いた書物に対して、オブライエンが返答した本だということになろう。
産業革命の時代にヨーロッパとアジアに差が開いた本当の理由
ここでは、オブライエンの議論について紹介しよう。
18世紀半ばまで、中国の経済的優位は有機経済として世界最高水準の国家であったが、ヨーロッパが産業革命により無機経済を発展させると、経済的地位は逆転した。そのためヨーロッパ人は、中国は伝統に固執し、その呪縛からから抜け出せないと考えるようになった。
ポメランツによれば、産業革命以前の数世紀間の両地域の経済は「驚くほど似ていた」のである。では、その後この両地域になぜ大きな相違が発生したのかということが、問われるべき課題となる。だが、そのために必要な統計は完備していない。「大きな問題は、ヨーロッパの研究者は、中国経済史の知識と理論構造に関する知識を欠いており、彼らが使用する数量的データの性質を理解することができていないことにある」のだ。
ヨーロッパと比較して低緯度に位置する中国は、生態系が豊かだった。ヨーロッパとは異なり、中国は無機経済への転換を経験することはなかったのである。しかし中国は、人口圧に対応することが困難になった。この点に、近世になり、中国よりヨーロッパの経済成長率がはるかに高くなった理由がある。
中国の農業は、粗放的・集約的であり、技術的進歩はあまりなかった。ヨーロッパとは対照的である。中国国家は、農業発展のために国家がインフラストラクチャーに投資することはなく、農業が発達しなかったので、人口圧を乗り越えて�、経済を発展させることはできなかった。それは、農業が発展したためマルサスの罠からの離脱に成功したヨーロッパとの大きな相違である。
イギリスには、大量の石炭が埋蔵されており、それを使用することで、熱量集約的な製造過程を維持することができた。ヨーロッパ諸国は、耕作地を周辺地域に拡大することで、都市化に対応した。中国同様、ヨーロッパも大陸間横断交易ではなく、むしろ地域内部の資源を活用することでマルサスの罠から離脱することができたのである。中国にも石炭は大量にあったが、それを動力として用い、手工業をベースとするスミス的経済成長から脱することはできなかったのである。
中国にあった石炭は蒸気機関の動力としては使用されなかった
オブライエンは、ポメランツの意見に同調することも、批判することもある。しかし何よりも重要なことは、本書がポメランツとの対話の本であるということであろう。
生活水準から判断するなら、ポメランツがいう1750年頃よりも以前に、ヨーロッパの水準が中国のそれを上回っていた可能性は高い。だが、その時期を明示することは不可能であろう。中国は、間違いなく、有機経済では世界最大の経済大国であった。オブライエンはポメランツ以上に、中国経済の水準の高さを評価する。中国はヨーロッパ経済とは違い、有機経済の段階=スミス的経済成長にとどまり、産業社会の形成に行き着くことはなかった。この点は、ポメランツとオブライエンの主張は同じである。
オブライエンはその理由について、ポメランツのいうように、イギリスで石炭が燃料源として使えた重要性は認めたうえで、中国にあった石炭は蒸気機関の動力としては使用されなかったことが、中国が産業資本主義経済へと至らなかった決定的な問題点であったと考える。しかし、ポメランツとは異なり、大西洋貿易だけではなく、ヨーロッパの周辺地域の農地拡大が、ヨーロッパの人々に食料を供給した意義を強調する。オブライエンは農業史家でもあり、その知識が生かされているといえよう。この点に、2人の意見の大きな相違がある。
オブライエンによれば、ポメランツの『大分岐』は、中国の衰退ではなくむしろヨーロッパの興隆の理解に寄与した。じつはこの点では、オブライエンの「大分岐」論もあまり変わらない。
オブライエンは、中国が有機経済から無機経済への転換に成功しなかった理由を、中国では石炭をエネルギー源として活用しなかった点にあると考えているようである。しかし、中国にもヨーロッパと同様に大量の石炭が埋蔵されていた。本来ならその石炭をうまく活用できなかった理由を説明すべきであるが、オブライエンは、それには成功していない。
現代社会を創出したのは、第二次産業革命だった
ここで一つ、オブライエンらの世界的に有名なグローバル経済史家の議論の問題点を指摘しておきたい。産業革命とは、長期的に見れば、有機経済から無機経済への転換を意味する。この転換に成功したヨーロッパと、失敗した中国に大きな経済格差がついたのは当然といえよう。ただしその過程は、18世紀後半のイギリス産業革命(第一次産業�革命)から19世紀末の米独の、第二次産業革命という。前者は綿織物を、後者は重化学工業を基軸としていた。
綿織物は軽工業なので、投下資本は少なくて済んだ。それに対し、重化学工業には多額の資本を投下する必要があった。そのためにドイツでは、銀行業が大きく発展することになった。イギリスとドイツの差異は、じつは二国の帝国主義政策の相違により生じた。
イギリスは広大な植民地を有していたので、カリブ海諸島で栽培された綿花を本国に輸送することで、第一次産業革命を発生させた。しかし、植民地をあまりもたないドイツでは、それはしょせん不可能であった。そのため、植民地を必要としない化学工業が発展したと考えられるのである。化学繊維は天然繊維よりもはるかに大量に生産することができ、しかも栽培のための土地が不要である。そのため、人口増のために必要とされる土地をより多く提供することができる。現代社会を創出したのは、第一次産業革命ではなく、第二次産業革命だったといえるのである。
このような長期にわたる過程の意義を、第一次産業革命だけに焦点を当てて論じること自体に大きな問題点があるように思われる。現代世界は、第一次産業革命ではなく、第二次産業革命の所産なのだ。それは、われわれが使用する耐久消費財は、煎じ詰めれば、多額の資本を必要とは、大規模な工場生産をおこなう第二次産業革命から出発したと考えられるからである。
このような問題点はあるが、オブライエンの『大分岐論争とは何か――中国とヨーロッパの比較』は、ここ20数年間の経済史研究の中核をなした「大分岐」に関して、も��っとも重要なエッセンスが詰め込まれた本である。本書一冊を読むだけでも、最近の世界の経済史研究でどういうことが論じられてきたのかということがある程度お分かりいただけるはずである。