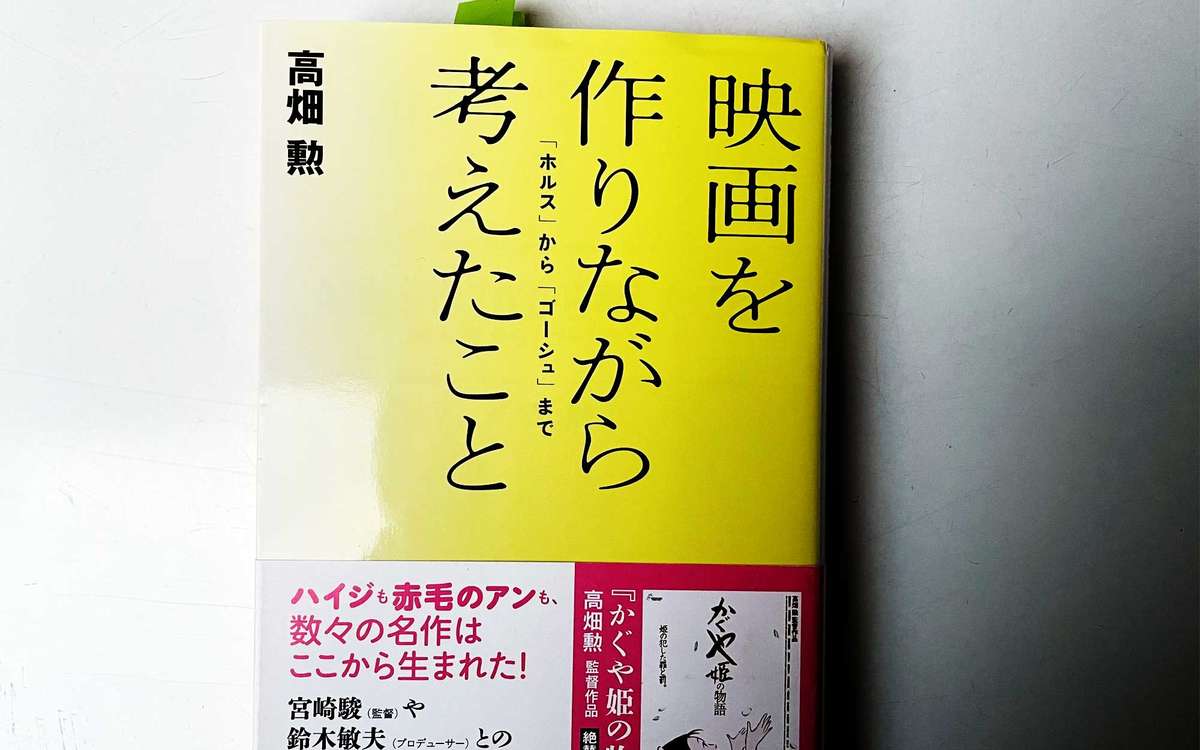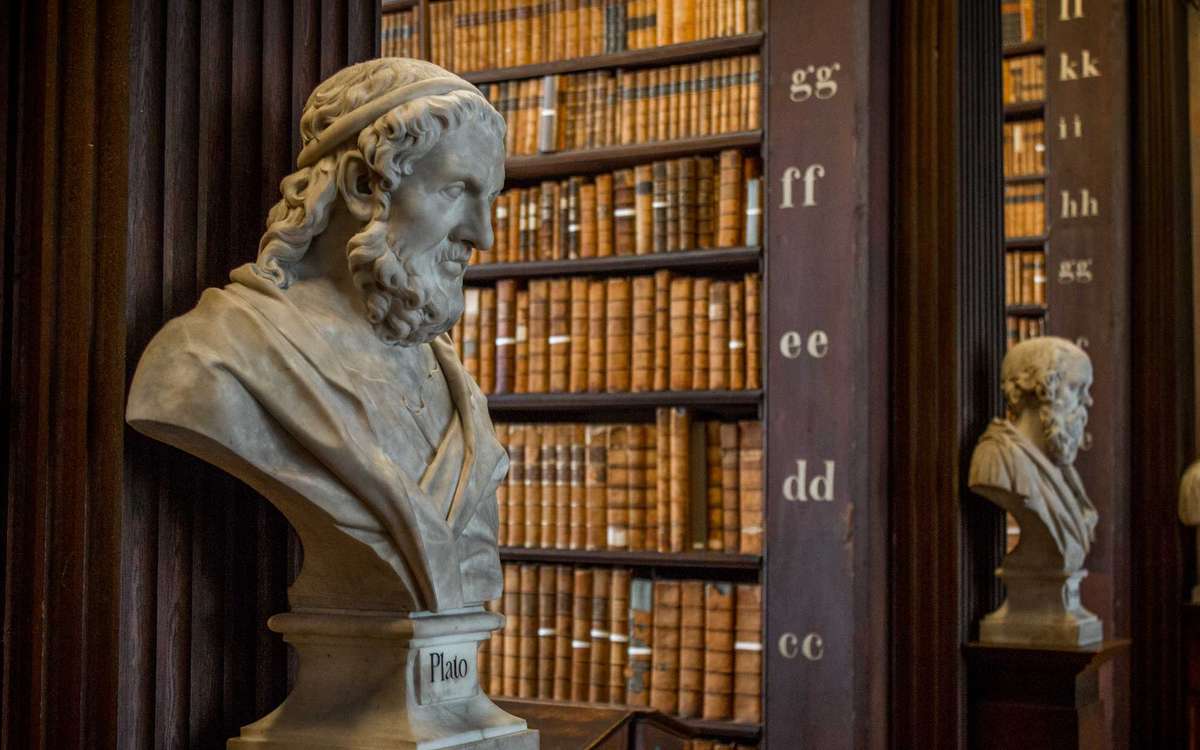社会主義リアリズムの影響を受けた「太陽の王子ホルスの大�冒険」
高畑勲監督作品「太陽の王子ホルスの大冒険」(1968年)は、アイヌの伝承をモチーフにした長編アニメーションである。宮崎駿が初めて本格的に製作に関わった作品でもあった。興行成績はふるわなかったものの、自主上映会を通してアニメーターやファンのあいだで知られるようになった(現在は、動画配信サービスで視聴が可能だ)。
主人公は少年ホルス。父と熊のコロと一緒に荒野で暮らしていた。父親の死をきっかけに、人間の村を探して、そこでの共同生活に加わるようになる。そのころ、悪魔・グルンワルドは人間たちを滅ぼそうと画策していた。グルンワルドは、妹のヒルダに命令して人間たちの心を操って、ホルスを村から孤立させた。その真の目的は、人々を疑心暗鬼にして仲間割れさせることである。しかし、ホルスは人間の連帯の力を信じ、村人たちを統率してグルンワルドと対決し、打ち勝つのだった。
https://www.youtube.com/watch?v=N4TLPi-qgKg
この作品は、明らかに社会主義リアリズムの影響を受けている。主軸となるストーリーラインは、未熟な青年が個人主義を乗り越え、仲間と協力しながら巨悪と戦い、新しい未来を掴んでいく成長物語である。これが多く�のビルドゥングスロマンと異なるのは、個人の人生上の〈内面的葛藤〉ではなく、迫り来る敵に対して連帯して闘うという〈行動〉に重きが置かれることだ。
「太陽の王子ホルスの大冒険」でも、物語の前半・後半で主人公ホルスの変化が描かれる。物語の前半の見せ場は、村を襲うオバケカマスとの戦いだ。最初はオバケカマスと村人たちが戦っていたが、一人の男性が亡くなってしまった。彼の妻は村人たちに向かって、一人で立ち向かうのではなく、みんなが協力して戦う重要性を訴える。ところが、ホルスは一人で村を抜け出して、オバケカマスと戦って勝利した。彼は村の英雄となった。この展開について、高畑勲は解説でこう述べている、
主人公であるホルスは力いっぱい生きようとします。しかし全てを一人で解決して来た彼は、村へ入ってからも、力を合わせることの意味やそのむつかしさを彼のセリフほどには理解していないのです。(高畑勲『映画を作りながら考えたこと』文春ジブリ文庫、2014年、24頁)
ホルスは、村に来るまでは個人主義的な生き方をしてきたのだ。それが、物語の後半では、悪魔グルンワルドに何度も負けそうになることで変化が生じる。グルンワルドの強さは、強力な武器や魔法によるものではない。彼は、人間の弱さや欲、嫉妬などの悪の心に漬け込んで心を操り、人々を対立させて自滅させる。そのことに気づいたホルスは、村人たちを説得して一人ではなくみんなと協力しようと呼びかけるのだ。
民衆に連帯と闘争を呼びかける、イデオロギーに満ちた作品
高畑は物語の後半のホルスをこう解説する。
ホルスのおかれた様々の状況を考えてみると、彼は何度も死んだり、挫折してあたりまえです。その彼が「悪魔」の意思に反して何度でも生き返ってくるのは、みんなの願望を一身に集めた不死身のヒーローであるためというより、やはり「何人ものホルス」(グルンワルドに対するヒルダのセリフ)であったのだと、考えたいのです。(同書、24頁)
ホルスというキャラクターは、唯一無二の個人ではなく、民衆の象徴として描かれている。無数にいる民衆のひとりひとりが、連帯の意志を持って巨悪と闘うなかで、「何人ものホルス」になり得るのだ。この作品は、ホルスの成長を見て楽しむ娯楽作品ではない。映画の鑑賞者であり、民衆に連帯と闘争を呼びかけるような、イデオロギーに満ちた作品であると言えるだろう。
そのなかで、村落共同体は美化されて描かれる。見応えがあるのは、音楽と動画で表現される、鮭の収穫、ホルスの歓迎の宴、結婚式の三つの場面だ。村人たちが声を合わせて歌いながら駆け回る様子が、見事なアニメーションで生き生きと表現されている。たとえば、一つ目の鮭の収穫の場面では、大人も子どもも男も女も、川に飛び込んで鮭を掴み取り、陸にあげて干し魚にする。みんな、くるくると踊りながら、豊漁の喜びを歌い上げる。たとえば、こんな歌詞だ。
のーぼれ、のぼれ/やーやーやー/のーぼれ、のぼれ/やーやーやー/鱗光らせて/やーやーやーや/川面を�埋め尽くし/やーやーや/いそげや、いそげや/陽の落ちるまで
これは漁師たちの労働歌を模している。ホルスもそこに加わって、共同体の一部となる。高畑自身も「漁や干魚作りなど集団労働、お祭りの踊り、村をあげての結婚式など、現在失われたかにみえる村落共同体の姿を集約的に描きだそうとした」(高畑、前掲書、237頁)ことには画期的意義があったと自画自賛している。彼は、アニメーション作品から徹底的に個人主義を退け、集団主義的な共同体の素晴らしさを謳い上げたのだ。
「個」であることで強烈な魅力を放つ、悪役の少女
ところが、奇妙なことが起きる。実際にこの作品で鑑賞者に強烈な印象を残したのは、イデオロギーに基づく主張ではなく、悪役の少女・ヒルダの魅力だった。アニメーションを研究するなみきたかしはこう述べる。
「太陽の王子ホルスの大冒険」を公開時に観た僕の世代は、みなヒルダにイカレてしまった。それは可愛いとか萌えとかいうものとは断じて違う。二次元の作られたものではなく、考え行動する、そして主張を持った一人の人間を感じて、忘れられない実在の人物となったものなのだ。(なみきたかし「もりさんのヒルダ」、『アニドウ』、掲載日不明)

アニメーターの西田亜沙子も、子ども時代に見たヒルダは肉感的で実在性があったと回想している(西田亜沙子「『太陽の王子ホルスの大冒険』ヒルダという「女性」の生々しい存在感」、『Febri』、2022年3月25 日、)。両者は、これはヒルダのキャラクターデザインを担当した森康二の力によるものだろうと類推している。私自身、この作品の視聴後には、悲しげな表情を浮かべたヒルダの顔が頭に焼き付いて残った。鑑賞者は、高畑の意図とは関係なく、村人の集団性ではなく、ヒルダの個別性に魅了されるのだ。
ヒルダは村人の対照軸として描かれている。彼女は決して集団の合唱には加わらず、いつも一人だ。ホルスとヒルダの出会いの場面でも、歌は重要な役割�を持つ。彼女は湖のほとりにある、もう滅んでしまった村の廃墟にぽつんといた。そして、竪琴を奏でながら「ヒルダの唄」を歌う。ホルスが話しかけると、彼女は「どこにも住めないの。どこの村でも私を住まわせてはくれないの」「私の村は悪魔に滅ぼされたわ。そして、私一人が助かったの。でも、私には悪魔の呪いがかけられている」と語る。ホルスが黙ってしまうと、笑ってみせ「いいの、それでも。寂しくなんかないわ」と続けた。ブランコにすわって、竪琴の弦を鳴らし「私には歌がある」と言うのだ。彼女の友だちはリスのチロと、白フクロウのトトだった。彼女は小鳥のような声で「高い梢の細い小枝に/歌うたう小鳥/いつもひとり/いつもひとり/ぴるぴるぴるぴるるる/りりりりる」と歌う。
ヒルダの村は悪魔に滅ぼされてしまった。彼女はひとりになってからも、歌をうたうことで生き延びてきた。人間がいなくなったあとも、動物たちと友だちになった。彼女に対し、ホルスは「本当は君も寂しいんだね。僕がひとりぼっちだったときみたいに」と告げる。それを聞いてヒルダは「あなたも? じゃあ、私たち兄弟ね、双子よ、きっとそうよ」と言い出し、虚空を見つめてブランコをこぎながら「双子だったのよ」とつぶやく。ホルスは「おいで、僕らの村に行こう。きっと喜んで君を迎えてくれるよ。そして君の歌をうたって聞かせるんだ。その竪琴で」と誘う。ヒルダも「行ってみたい、もし住まわせてくれるなら。そして思いっきり歌ってみたい」と答えた。
異なる人間の在り方を受け入れない人たち
ホルスとヒルダの会話は噛み合っている��ようで、ずれている。ホルスにとって、死者や動物たちは友だちにカウントされない。村に来る前の彼も、父や熊のコロと一緒に暮らしていたが、その存在は無意識に外されている。彼は人間の共同体以外に価値を見出さない。ヒルダはホルスの価値観に乗っかっているかのように、私たちは同じだと言う。そのことを理由に自分たちは「双子だ」と言い出している。ホルスはそれを無視して村へ来ることを誘った。彼の考え方では、ヒルダも人間の共同体の一員になって、孤独から解放されるべきなのだ。ヒルダはホルスの誘いに応じながらも、村では歌をうたうことしか考えていない。もちろん、彼女が歌いたいのは労働歌ではなく、自分自身の歌だ。
実際に村にやってきた彼女が歌い始めると、村人たちは仕事をやめて聞き入ってしまう。「ヒルダの子守唄」と題された曲にはこんな歌詞がついている。
昔、昔、神様が言いました/おやすみ、みんな/優しい私の子どもたちよ/昔、昔、かわうそがいいました/お願い、神様/黒熊の腕に鉄鎖/おやすみ、かわうそよ/黒熊の腕はもうはねた/昔、昔、熊どもがいいました/お願い、神様/かわうそが小魚荒らします/おやすみ、熊たちよ/かわうそたちは/もう火にくべた/昔、昔、神様が言いました/おやすみ、みんな/優しい私の子どもたちよ
ヒルダが歌うのは神話世界である。熊とかわうそが登場し、お互いに自分を利するように神様にお願いする。神様は両者の願いを聞き入れたため、どちらも腕をはねられたり火にくべられたりする。つまり、個人主義的に利己に走った者たちは、結果として報いを受けるのだ。内容が残酷であるにもかか�わらず、ヒルダが澄んだ声で歌うと、村人たちはぼんやりと惚けてしまう。まるで歌による催眠効果で、お互いが争い合って共同体を分裂させるように洗脳しているかのようだ。彼女の歌は、村人たちの連帯していくための労働歌と対極にある。共同体にやってきても、彼女はそこに一体化せず、独立した表現者として歌をうたうのである。
彼女が集団の一部となることをはっきりと拒む場面もある。村娘の一人が結婚することになり、女性たちが集まって花嫁衣装に刺繍をしていた。そこに呼び入れられたヒルダは、花嫁のお祝いの儀式として一針刺繍をするように求められる。周りがそのうちヒルダはホルスと結婚するのだと囃すと、彼女は動揺して針を指に刺してしまう。すると「針も使えないんじゃ、お嫁にはいけないね」と笑われてしまった。彼女はそこで激昂して「なんになるの、こんな着物が。無駄よ、いくら飾ったってこんなもの火をつければ燃えてしまうわ、ただの灰よ」と叫ぶ。ベールをかぶせられると、一瞬戸惑った表情はするものの振り払い、「刺繍なんてできなくたって、もっと私にはできることがある」と飛び出していく。彼女は、村の女性たちの輪に加わり一緒に生活していくことに惹かれながらも、それに抵抗する。
高畑は、ヒルダと村人たちの関係について「卑小なはずの村人たち(「人間」)の「生きるよろこび」に圧倒され、自己を失うまいともがき、崩れかかる自分をとり戻すためにのみ、村人たちやホルスを苦しめる行為を行うのです(高畑、前掲書、26-27頁)」と述べている。私にはそうは見えなかった。ヒルダは孤独に苛まれても、歌に生きがいを見��出してきた。彼女はすでにアイデンティティを確立し、自己に誇りを持っている。しかし、ホルスも村人たちも個としての人間・ヒルダを受け入れない。むしろ、個人的な過去の記憶を捨て去り、共同体の一部になることを望む。それこそが幸せだとかれらは信じて疑わない。異なる人間の在り方を受け入れないのだ。
自分が正しく、相手は間違っている
作品では深く描かれなかったヒルダの内面を想像してみよう。彼女の村は、悪魔・グルンワルドに滅ぼされた。グルンワルドにそそのかされた大人たちが、お互いを罠にはめ、貶め、裏切り合う。彼女は、少女時代に人間の最も醜い面を見てしまったのだ。その点は、ホルスが父に守られ、その惨状を目撃せずにすんだのとは決定的に違う。彼女の心には深い傷が残ったはずだ。だから、村にやってきた彼女が自分のトラウマをえぐる自傷行為を繰り返しているように見える。彼女は、成長した後も人間の虚栄心や競争心、嫉妬や裏切りに敏感ですぐに察知する。だからこそ、彼女は人間たちをそそのかさずにいられない。そして、人々が憎み合うのを見ると「ほらみろ、やっぱり人間は裏切るのだ」と、人間不信を募らせていく。彼女は人間を信じたいが、信じられない。そこにヒルダの孤独がある。
その孤独を分かち合えるかもしれないと思ったのが、ホルスだった。彼女にとって、ホルスは恋人ではなく「双子」になって欲しい存在だった。同じ場所で生まれ育った、深い傷を抱えた孤独な存在。「双子」としてイメージされるのは、身を寄せ合ってともに生きていくことができる運命共同体としてのペアだろう�。ところが、ホルスはそんなヒルダの心の機微を理解できるようなタイプではなかった。
物語の後半で、ヒルダが自分は悪魔の手先であると告げると、ホルスは「違う、ヒルダは悪魔なんかじゃない。いや、もしそうでも君なら人間になれる、人間に戻れるんだ」と叫ぶ。だが、彼は彼女のこれまでの人生に全く関心がない。なぜ、悪魔になる道を選ばざるを得なかったのかにも興味がない。そして、彼女に過去のことは忘れて人間(村人)になれと説得する。その後も、ひたすら「ヒルダ〜」と彼女の名前を連呼し、自分の元に帰ってくるように求める。自分が正しく彼女が間違っていると確信しているのだ。だから、彼女の声に耳を傾ける気はない。そしてヒルダの幻影を追って彷徨い、そのうち「そうか! わかりかけたぞ!!」と一方的に納得する。ヒルダの中には〈良いヒルダ〉と〈悪いヒルダ〉がいるのだと決めつけるのだ。
ホルスとヒルダの会話は、DV加害者が被害者を追っている構図のよう
ホルスが現実のヒルダと再会しても、二人の会話は噛み合わない。
ホルス「ヒルダ! 行こう、一緒に村へ」
(ヒルダは眉をしかめる)
ホルス「僕は間違ってなかった。そして君のなかのもうひとつのヒルダを、君の手で、そして僕らの手で必ず追い出せるって気づいたんだ。さあヒルダ、帰ろう、村へ帰るんだ」
(ヒルダが剣を振りかざし、ホルスを攻撃し始める)
ホルス「そのヒルダを、そのヒルダを追い出すんだよ。負けるんじゃない、本当のヒルダがどんなに強いかを思い知らせてやるんだ」
(�ヒルダはホルスに打ち負け、剣を落としてしまう)
ホルス「わかったね、君はもう人間なんだ」
ヒルダ「さよなら、ホルス」
(ヒルダは吹雪の中で消えていきながら、ホルスに告げる)
ヒルダ「兄さん(悪魔・グルンワルド)が村へ行ったわ。早く、フレップやマウニ(村の子どもたち)を助けてあげて」
書き起こすと、まるで不条理劇のような会話だ。二人は全く噛み合っていない。高畑は「ヒルダにとって、意気軒高たるホルスの姿、斧をふりかざして『君の中のもう一人のヒルダを追いだすんだ』とつめ寄るホルスの姿は不可解な、恐怖の対象でしかなかったのです(高畑、前掲書、28頁)」と述べるが、私は鑑賞者として、まさにそのヒルダの気持ちを抱いた。
この場面は、DV加害者が被害者を追っている構図と重なって見える。加害者は、被害者の言葉に耳を傾けることはない。一方的に被害者を自分の家に連れ帰り、そこに閉じ込めて支配しようとする。加害者は、それが被害者のためになるとかたく信じている。このような加害者に対して被害者ができることは、逃げることだけである。彼女がホルスから去っていくときに見せる表情は諦めのようだ。自分が理解されることはないことを受け入れたのか。

他方、ヒルダが心配するのは、自分ではなく子どもたちだった。そして、命を投げ打って雪山で遭難した熊のコロと子どもを助けた。彼女は最後まで人間一般(大人)ではない者、つまり子どもと動物たちを愛し、死んでいくことを選んだ。
作品の最後では、奇跡が起きてヒルダが生き残り、村に帰ってくる場面が描かれる。彼女が不安げな顔で村に近づいていき、ホルスと再会するところで、アニメーションは終わる。二人は結婚してこの村で暮らすのだろうか。刺繍をして、労働歌を歌うのだろうか。ここで彼女は幸せになれるのだろうか。アニメーターの西田亜沙子は、この点について次のようにコメントしている。
(前略)ヒルダは村に受け入れられて、居場所を見つけたあと、否応なしに農村社会の中に組み込まれていく。たぶん、映画のあと、ホルスと結婚した彼女は子供をもうけて、刺繍や料理をしながら暮らしていくんだろうな、と想像できるんです。そういう意味で、ひとりの人生がアニメの中にすべて入っているんだな、と感じます。(西田、前掲)
私はそうは思えなかった。ヒルダはどんなにホルスに詰め寄られても、自分を一度も曲げなかった。命を落としかけても、自分の意志を貫いて納得のいく選択をした。彼女は自立した個人であり続けた。強靭な自己を持っているのだ。
他��方、この作品のなかで、村で暮らすことは自己放棄と集団化への一体化を意味する。それを選べば、竪琴を奏で、山や湖に向かって一人で歌う彼女の精神が潰されていくだろう。もし、彼女が生き延びても、山を降りずに動物たちと歌って暮らしていたとすれば? そんな夢を見る。彼女が一つの村にとどまるのではなく、各地を転々としながらアーティストとして自由に生きていく姿を私は観たかった。人間の生き方は個人か集団かの二択ではない。もっと柔軟に、いろんな方法で人と繋がりながら、自由に生きられるはずだ。「ヒルダの人生に必要なのはホルスではない。別の人間だろう」と私は思った。
理想的な共同体を表現しようとしたら、その先の社会運動を予兆させるキャラクターが生まれてしまった
もっとも高畑にとって、私が夢見るようなヒルダの結末は問題外だろう。この作品では、性別分業制がはっきりと描かれている。男性は外敵と戦い、女性は家を守るのだ。作品内で、男性たちは対立して分裂を繰り返す。そのたび女性たちは一致団結を呼びかけるが、男性たちが耳を貸すことはない。女性たちは、料理や刺繍、出産や育児などの再生産労働に従事し、共同体を維持することだけに価値を見出される。高畑は意識的・無意識的に当時の労働運動内の性差別もこの作品に盛り込んでいる。ところが、ヒルダはそこに収まり切らない。期せずして、彼女は70年代以降に大躍進を遂げるウーマンリブやフェミニズムなどの、女性たちの自己確立を求める社会運動の波を予兆させる。高畑はイデオロギーに基づいた理想的な共同体を作品内で表現しようとしたに�もかかわらず、その範型からこぼれ落ちる女性像を自ら生み出してしまったのだ。
同時にそれは、宮崎駿がのちに生み出していく、自分の道を切り拓き、自己実現を叶えていく少女たちとも時折、重なって見える。「太陽の王子ホルスの大冒険」では、強烈に自己を持った少女は成長を阻まれ、共同体への参入以外の道は示されず、それに従うしかなくなってしまった。だが、ヒルダのような少女たちも、宮崎の作品であればもっと広い世界へ羽ばたけるのではないか。
「太陽の王子ホルスの大冒険」は、若き日の高畑勲や宮崎駿が苦闘のなかで生み出した作品で、決して完成度は高くない。かれらの試行錯誤の痕跡が残る、実験的作品なのである。高畑自身がこのように1983年に回想している。
今ふりかえって考えてみますと、ホルスの人物像にそしてヒルダの扱いに、多くの混乱がみられることに気づかざるを得ません。象徴的な英雄神話的なものに、きわめて現実的な諸問題や、環境をからませていったために、物語の力強さを大きく損なってしまいました。力不足を痛感しています。(高畑、前掲書、29頁)
また、彼は「ぼくたちの青春の一時期のすべてを注ぎこんだともいえるたいへんに思い出深い作品」(同書、242頁)と語り、スタッフが総力をあげて取り組んだことを強調している。なかでも、宮崎の貢献を振り返ってこんなふうに書く。
もし宮さんが、当時あの想像力とエネルギーで、自分の考えをおもうさま追求し表現していったとしたら—それはもちろんあり得べくもなかった仮定にすぎませんが—彼はいったい��。どのようなものを作りあげたのでしょうか。(同書、243頁)
もし、宮崎が「太陽の王子ホルスの大冒険」を監督して、ヒルダを描いたら? 私にも想像のつかない世界だ。他方、宮崎駿監督作品「千と千尋の神隠し」では、湯屋を舞台に、突然、労働現場で働くことになった少女の姿を描いた。彼女は否が応でも労働者たちの共同体に組み込まれていく。宮崎は労働と共同体の関係をどのように描いたのだろうか。次回はそこに迫ってみたい。
参考文献
高畑勲『映画を作りながら考えたこと』(文藝春秋 2014年)