「自然を守る」というスローガンは嫌になる
宮崎駿の映画作品のテーマの一つが「人と自然の共生」であることは広く知られている。人間の産業社会の発展とともに、豊かな自然やそこに住まう精霊や神々が滅んでいったことが、繰り返し彼の作品の中では描かれる。他方、宮崎自身は頑ななほど環境主義者とみなされることを嫌う。エコロジストだと思われたくないからタバコをぷかぷか吸うのだと言い、「自然を守る」というスローガンは嫌になると語る。(宮崎駿『出発点』徳間書店、1996年)彼の環境保護に対する姿勢は捻れている。
米国のエコロジスト、アーネスト・カレンバックとの対談では、宮崎の環境に対する考えがより明瞭になっている。(宮崎、1996年)カレンバックは小説『エコトピア』(1975年)で、持続可能な理想的ライフスタイルのモデルを描き出した。その作品を題材にしながら、宮崎とカレンバックは、環境思想の二つの極について議論する。一方の極は、現代文明を捨て、森の中で自然と調和して暮らしていくような環境思想である。このとき、人間の技術発展による快適な生活は放棄せざるを得ない。他方の極は、決定的な地球の破滅を防ぐために、自然に対する害の少ないライフスタイルを目指す環境思想である。この場合、現代文明のもたらす安全や快適さを維持しつつ、人間社会の欠点を修正していくことを目指す。
カレンバックは後者の立場であり、米国に住む人々が環境にやさしい暮らしに転換することで、先進国のおかした環境破壊の過ちを避けて、発展途上国が異なる産業社会を実現するのではないかと提起する。それに対して、宮崎は悲観的な見方を示す。エコトピアのような米国発の環境思想が出てくる前から、アジアもアフリカも自然と共生する生活スタイルを持っていた。しかしながら、現代の国際社会は、環境破壊をしてでも経済成長し�なければ国が生き残れないような状況にある。
自然を守るために、貧乏や病気、早死を受け入れられるのか?
宮崎は、もし共生型の異なる社会を目指すのであれば、私たちは貧乏や病気、早死になどを受け入れ、それが自然のサイクルであると考えるしかないと述べる。しかしながら、ほとんどの人はこの論に賛同しないだろう。宮崎はこう語った。
(前略)長生きしたい、貧乏したくない、お腹いっぱい食べたい、その結果、こういう状況にきた。やり方を間違えたからじゃなく、文明の本質の中に、こういう事態を起こす原因があったのだと思う(後略)(宮崎、1996年、339頁)
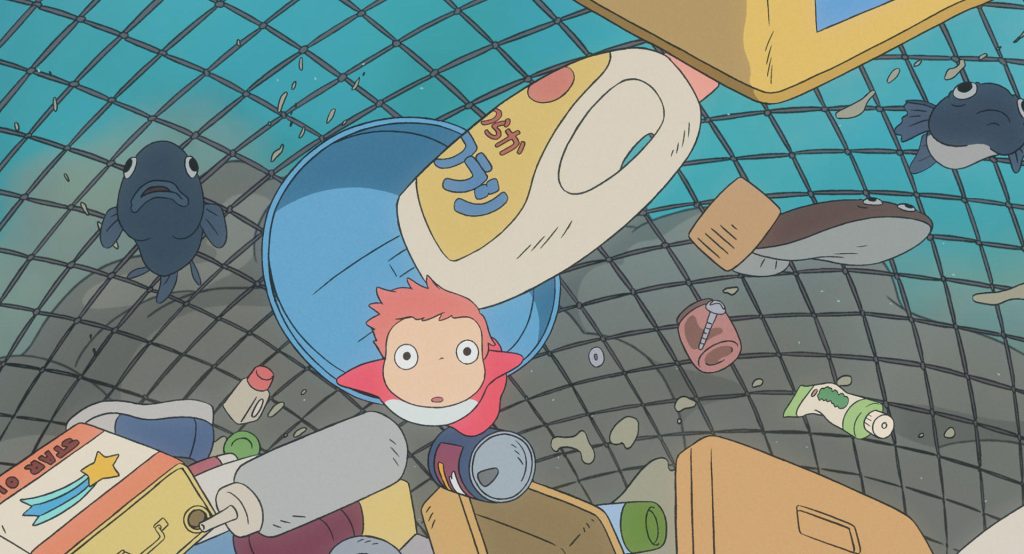
この宮崎の環境思想の核にあるのは「人間の矛盾」である。ひとりひとりの私たちの心にある欲望によって、人間は安寧な暮らしを求め、幸せを追求する。その欲望こそが、産業を発展させる一方で、自然を破壊した。宮崎は、人間の欲望を否定したり、批判したりす��るのではなく、生まれつき持っているものとして受け入れる。そのうえで、結果として起きる自然破壊を直視し、人間にはその責任があるとする。同時に、彼は「人間に自然を守れるのか?」という疑問も持つ。公害問題の水俣病を取り上げ、次のようなエピソードを紹介する。
(前略)水俣湾が水銀で汚染されて死の海になった。つまり人間にとって死の海になって、漁をやめてしまった。その結果、数年たったら、水俣湾には日本のほかの海では見られないほどの魚の群れがやってきて、岩にはカキがいっぱいついた。これは僕にとっては、背筋の寒くなるような感動だったんです。人間以外の生き物というのは、ものすごくけなげなんです。(342頁)
続けて、宮崎は「彼ら[引用者注:水俣の海の生き物たち]は、人間がバラまいた罪悪を一身に引き受けて生きている」と付け加える。つまり、水俣病において、海の生き物たちは人間の犠牲となりつつも、決して生きることをやめず、同じ海で暮らし続ける。彼はそこに自然の力を見出す。
原生自然だけが価値のある自然ではない
宮崎の環境思想では、自然は一方的に破壊されたり、守られたりする存在ではない。どんなに虐げられても、生命の営みをやめない生き物たちへの敬意が、彼の思想の核にある。
こうした宮崎の環境思想に基づく自然保護の理念は、地域に密着した小規模な活動へと向かう。彼は「トトロの森」(埼玉県所沢市を本拠とするナショナルトラスト運動「トトロのふるさと基金」によって保全される��森)に関わっている。宮崎いわく、「トトロの森」を支えるのは長年、地元で探鳥会をやってきたような地道な人たちで、柔軟でオープンな活動を進めている。たとえばみんなで集まって、「笹を切るのも気が引ける」「落ち葉はそのままにしておいてはどうか」などとお互いの意見を交換しつつ、ぼちぼちと森の保全に努める。そのような活動について、「とりあえずできることをやる」(200頁)のだと、宮崎は言う。
こうした森の保全活動には、人間の手が入っているから本当の意味で「自然を守る」ことにはならないという批判もある。たとえば、環境思想には「原生自然(wilderness)」という概念がある。「原生自然」とは、人間がこれまで一切、関与したことのない、未開状態の原初的な自然である。たとえば、米国のヨセミテ渓谷は代表的な原生自然であるとみなされた地域のうちの一つだ。それに対し、宮崎は人の関与の有無によって自然の価値は変わらないとする。彼は「人が植えた木だから自然の木じゃない、原生林にならないから大事にしてもしょうがないんだと言ってるよりも、人がつくった森でも、森としてちゃんと機能して、想像もつかない複雑な生態系になったりするんだと思うほうが、僕の気持ちに合います」(201頁)と主張する。ここにあるのは、人間を超えた自然界の生命の営みの豊かな可能性への信頼だ。彼は次のように言う。
たとえば、僕らがこの事務所のわきにケヤキの木を植えることはできる。だけど、この木がどうなっていくのかというのは、分��からない。この木が人に何をもたらすか。恋を生むきっかけになるのか、ただ倒れてきてこのビルがかしぐきっかけになるか。それは予見できないことです。予見できると思うのは傲慢です。(200-201頁)
人工林にも神は宿るかもしれない
さらに宮崎は、「人間のために必要だから森を残そうっていうふうなその能率的な発想で自然を考えるのは、なんかやっぱり違うんじゃないのかなあという気がしてね」(494頁)と語り、自然科学では捉えられない超自然的な存在についても発言している。彼はオカルトではないと断りつつ、この世界にあるのは「五感だけで感じられるものだけじゃないでしょう」(494頁)と問いかける。

宮崎は「アニミズムはぼく、好きなんですよ」(472頁)と明言している。また、アニミズムとは森の中には「何かがいる」と感じるような、日常経験に根ざすのだと考える。日本では神様は闇の中におり、森の奥深いところや��山の中に住み、依代を建てるとふらっとやってくる。古い神社では、今でも御神体は石や木である。薄暗いところに置かれたモノが信仰の対象になっている。ぼんやりとしてよくわからない不気味なものに対し「こわい」という畏敬の念を持つことに、宮崎の考えるアニミズムの核がある。彼は神聖な森と人々の心はつながるのだと言う。
そういうの[引用者注:神様が住んでいるような森]は自分の心の奥深い暗がりとどこかでつながっていて、そういうものを片方で消してしまうと、自分の心の中にある暗がりもなくなって、なにか自分の存在そのものが薄っぺらいものになるという感じがどこかにあるもんで、気になるんですね。(494頁)
このように、宮崎の森の保全活動は、スピリチュアルな発想と地続きである。私たちの精神世界の奥底は、薄暗い森につながっており、そこには神様たちがいるのである。
さらに、このような森は原生自然ではなく、人間の手の入った人工林にも宿る。彼は次のように言う。
人間は、きっかけをつくるとか、物を据えるというのはするけれども、そこに何が宿るか、神様が宿るか、宿らないかというのは、自分たちが決められることじゃない。この世の中を見ていくやり方としては、どうやらこういうほうが当たっているらしいですよ。(201頁)
人間が、神を招くために森を作り、神をコントロールして住ませることはできない。しかしながら、森を用意することで、そこには神が宿るかもしれない。その可能性を宮崎は示唆している。したがって、彼にとって森の保全は、物理的・自然科学的な環境保護であるだけでは��なく、自分たちの心の平穏を守るための活動でもある。
大量の電気を使いながら、自然を思う矛盾
ここまで見てきた通り、宮崎は真剣に自然と向き合っている。それも地元でのコツコツとした緑の保全活動に加わることで、観念だけではなく行動によって、人間と自然の共生を少しでも可能にする方法を探っている。ところが、彼の職業はアニメーション監督である。ふだんの仕事では、コンクリートの建物の中で、電気を大量に使いながらフィルムの作製に血道を上げている。映画館やテレビ、コンピューターの画面で上映されるアニメーションはまさに機械の生み出すイリュージョンである。彼は、職業的には「自然を守る」どころか、破壊を推し進める産業に従事する。その結果、彼の作品を通して、現代の子どもたちは自然の中で遊ぶのではなく、人工的な世界に耽溺していく。
その矛盾を誰よりも深く自覚しているのが、宮崎自身である。彼は自然の美しさは、目まぐるしく起き続ける変化にあるという。それを描くことができるのが動画であるアニメーションでもある。
(前略)自然という現象を描くときに、例えば空気というものも、それから植物も光も全部、静止状態にあるんじゃなくて、刻々と変わりながら動態で存在しているものなんですよね(中略)それを見ている人間も歩いている自分も、その感受性も刻々と変化するでしょう。いつもなら「いいなあ」と思える景色が、今日は条件が全部揃ってるのに全然目に入ってこないとかね。それから、なんでもないくだらない状況なのに、やたらに景色がよく見えるとかね(笑)(中略)そ�れは、みなさん経験してるものだと思いますよ。そうすると、こう「いい景色ですね」って言うときに、ただ一枚絵を描いただけで済むっていうものではないはずだっていう、そういう強迫観念はありますね(宮崎駿『風の帰る場所』文庫版、2013年、27頁)
アニメが自然に触れる機会を奪っている
ところが、このような自然を作品の中で描こうとする時に、アニメーションの表現には限界があり、出来上がった動画を見て「本当の風景に比べると、自分たちのやってることは情けないなあ」(28頁)と感じると言う。そうだとすれば、アニメーションではなく、実際に自然の風景を見にいく方が良いのではないか。彼自身もこのように述べている。
ずっとセルアニメをやってきて、できることよりできないことのほうが多いと感じる近頃だが、それでも子供のときに素晴らしいアニメーションに出会うのは悪くない体験だと思う。そういいつつ、ぼくらの職業が実は子供の購買力を狙う商売なのも十分分かっている。どんなに良心的と自負しても、映像作品は子供の視覚と聴覚だけを刺激して、子供たちが自分で出かけて発見し、肌に触れて味わいとる世界を、その分奪っていることも事実なのだ。(宮崎、1996年、114頁)
宮崎のこの葛藤とは裏腹に、彼の作品は映画、テレビ、動画サイトで配信され、多くの子どもたちを魅了している。日本国内だけではなく、世界中の子どもたちが彼のアニメーションに夢中だ。作品が環境教育の素材として使われることもある。宮崎がど�んなに拒もうとも、彼とその作品は環境運動のシンボルの一つとなっている。彼の環境思想における理念と作品の間には矛盾がある。
それでは、宮崎は実際の作品において、「人間と自然の共生」をどのように描くのだろうか。矛盾に直面してもなお、製作しつづける作品にはどのような意義があり得るだろうか。次回は宮崎駿監督「もののけ姫」を取り上げたい。彼の環境思想の理念がどのように作品内で反映され、子どもたちに伝えられているのかについて、考えていく。
参考文献
『出発点』宮崎駿(徳間書店 1996年)
『風の帰る場所―ナウシカから千尋までの軌跡』宮崎駿(文藝春秋 2013年)








