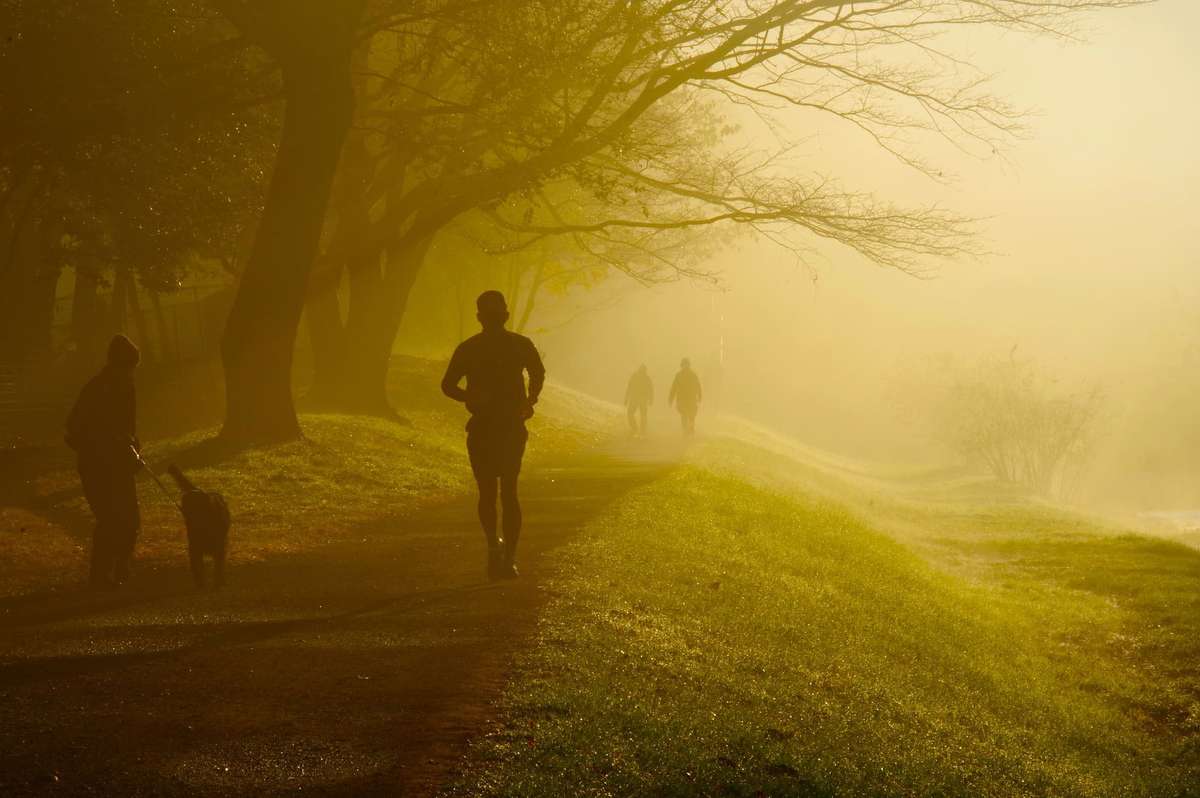ミース・ファン・デル・ローエの蔵書、それは秘密
モダニズム建築の巨匠ミース・ファン・デル・ローエ(1886−1969年)。建築界では世界中「ミース」で通じる。20世紀後半の世界の建築と都市は、多かれ少なかれミースの提唱・実践した「ユニバーサル・スペース(均質空間と訳されることがある)」に影響を受けている。バルセロナ・パヴィリオン(1929年、バルセロナ万博のドイツ館)、ファンズワース邸(1950年、アメリカ)やシーグラム・ビルディング(1958年、アメリカ)等は20世紀を代表する建築に数えられるし、ミースのデザインによるバルセロナ・チェアは日本のオフィス・ビルのラウンジ等でもしばしば見かける。“Less is more”や“God is in the detail”というミースの言葉も有名だ。
そのミースは、ナチスの台頭著しい1933年、母国ドイツを離れアメリカに亡命した。その後ドイツに残った知り合いに依頼して、最低限自分のそばに置いておきたい本を300冊ほどアメリカに送らせたという噂がある。私はこの話をイリノイ工科大学でミースの教え子だった高山正実さん(故人)から伺った。当時ミースが大学に来るのは2週間に一度程度で、葉巻を吸い終わるまでの時間だけ大学に滞在したという。学生にとって、めったに会えないこのカリスマに直接聞いてみたいことは山ほどある。ある時学生の中から「先生は厳選した300冊の蔵書のリストを作り、ドイツの知り合いの方にそのリストにあるものをアメリカに送るように頼んだとお聞きしましたが、一体どんな本を送ってもらったのですか?是非お教え下さい」という質問が出された。ミースは葉巻の煙をくゆらせながらガハハと笑い、「その質問には答えない。なぜならその300冊は私にとって意味のある300冊であって、君にとって意味のある300冊ではないからだ」と言い放ってゆっくりと立ち去ったという。戦後日本において、学校では先生の言うことを聞いて真面目に勉強するものだと教え込まれ、実際早稲田大学まではそうして育ってきた高山さんだったが、イリノイでこのカリスマの一言を聞いて「勉強は自分で求め、自分で探し、自分でするものなのだ」と、まさに目から鱗だったと話して下さった。
大学院生時代に刺激を受けた2冊
私としてはとっておきのミースの話だったので、ついつい書いてしまったが、厚顔無恥ついでに「私にとって意味のある本であって、君にとって意味のある本ではない」本について書かせて頂く。今から40年程前の1980年代前半、私が大学院生だった時期に読んで刺激を受けた本、その中でも瞬時に頭に浮かぶ2冊について。
1冊はスタッズ・ターケルの大著「仕事!」(中山容他訳、晶文社、1983年)。133人の実在の、多くは無名の人々に対するロング・インタヴューだけで構成された実にユニークな本である。ターケルは、115もの職業の人々を選び、その人々の仕事についての本音を聞き出す。人類社会を理解するとはこういうことだと強く認識させる、それこそ「大仕事!」である。イントロダクションの「仕事・ふつうの人のふつう以上の夢」に次のようなくだりがある。
「『われわれに、すべての人を食べさせ、着せ、住まわせる能力はある。これはまちがいない。問題は、人がたえず何かに専念していて、それが現実と接触しているようにするために、どれだけの方法が発見できるかということだ』。たしか、われわれの想像力が、いまだかつて十分に試されたことはなかった。それは確かだ。」
若い私は、建築という分野には「人がたえず何かに専念していて、それが現実と接触しているようにするため」の��方法が様々に用意されているように思われたし、それが可能性としてしか存在していないのならば、自分の想像力を試してみるのに相応しい分野のように思えて、わくわくもした。
そして、もう1冊は当時の指導教授、内田祥哉先生(故人)から「松村君、これ持ってる?持ってなかったら上げる」と言われ、遠慮なく頂戴した非売品の1冊というか、3冊の薄い冊子がセットでこれも薄い箱型紙ケースに入っていた「工業化への道」(不二サッシ、1962年)である。その時点で既に20年も前の本で残部も少ない貴重本のように思われたが、私自身、1980年代前半の「脱工業化」の時代に「工業化」をテーマに掲げていた少々珍しい学生だったので、内田先生は今後この「工業化への道」を渡すべき学生も現れまいとお考えになったのか、幸いにして直接頂戴できた。そして、この「幸い」感は、これら3冊の薄い冊子を読んだ後に大きく広がった。内田先生ご自身も書かれていたし、建築家で東京大学生産技術研究所教授の池辺陽さん、建築評論家の藤井正一郎さん、建築史家で早稲田大学教授の渡辺保忠さんといった、1962年には30歳代後半から40歳代前半の新進気鋭だった論者たちが、まさに時代の波頭にあったテーマ「建築生産の工業化」に正面から向き合って書き上げた論考の連続だった。

中でも一見「工業化」などと無関係な建築史家の渡辺保忠さんがここに書かれた歴史観が私の心に強く響いた。何の歴史観かと言えば、まさに「ものづくり人」がじわじわと広がり、日本の建築文化の基層を厚くし、すべての庶民が高度な建築技術を享受できる状態にしてきたという歴史観であり、このことこそが今日(1960年頃のこと)話題になる「工業化」と直接に関わると渡辺は言うのだった。
ものづくり人はどこから来たのか
現代に繋がる大工等のものづくり人の起源について語るのに、渡辺は原始から古代への飛躍を可能にしたのは何かという問いから始める。
読者の皆様もよくご存じの法隆寺や唐招提寺に代表される古代の建築群は、それ以前の登呂遺跡に見られる住居や倉庫といった原始の建築と比較すると、より高度な技術を駆使してつくられたものだという印象を与える。しかし、渡辺は次のように言う。法隆寺金堂の構造体をつくるために必要とした木工技術にせよ、基壇や礎石を築くのに必要であった石工技術や塔の相輪の鋳造技術、彫金技術��にせよ、瓦をつくるために必要であった高温度焼成の技術にせよ、すべて原始末期に準備されていたものに依存できる性格の技術だった。古代建築の飛躍発展は、こうした要素生産技術の進歩によったのではなく、それらを建築に結集し統合する生産の仕組みの確立によったと考えるのが適当で、その背景には、古代国家の権力によって集めることができるようになった大規模な民衆の労働力と、それを指導しながら効率良く組織化する能力を有した指導工人の官僚組織の成立があったと。
この古代の官僚組織における建設技術者のトップの役職名こそが「大工」だった。*¹ 平安時代中期(10世紀)に編纂された律令の施行細則「延喜式」では、宮廷の建設工事を担う木工寮工部は、統括責任者である大工1名とそれを補佐する次席の少工1名の下に、各工事を担当する木工、土工、瓦工、ろくろ工、桧皮工、石灰工等の技術責任者である長上工13名、専門技術者である番上工数十名、更に彼らの指揮の下で働く駆使丁、飛騨工といった労働者300名ほどで構成されていた。つまり、この時点では大工は官僚組織である木工寮工部にただ一人だったのである。
平安末期には、いわば国家事業としての造営の建設費を国司や貴族が負担するようになり、官僚組織の技術者もそれら貴族に雇われる技術者「雇工」に変化していった。そして、それとともに「大工」の人数も増えていった。ただし、この時点でそうした高級な技術者が働いていたのは、一部の特権階級による建築に限られていた。
渡辺は、それが大きく変化するのは、大規模な築城と�城下町の建設が一段落した元和年間(1620年代)を過ぎたあたりからだとしている。それまで一部の支配階級の建築にのみ必要とされていた大工技術とそれを支える職人が、需要の急減に対応すべく職場を拡大し、都市の町屋や比較的富裕な農家の建築に従事するようになったというのである。古代には特別な国家的事業にしか使われていなかった専門技術者による高度な木造建築技術が、時代とともに適用範囲を広げ、ついに近世になってすべてのとは言わないまでも、各地の多くの階層が利用できるところにまで普及したことになる。
要約すれば、この大工を代表とする練磨されたものづくり人の数の増加と、近世に完成形に近付く道具の発達とが、日本全体の建築の生産性を飛躍的に向上させたというのが、渡辺の言わんとするところだった。
明治以降の日本の建築生産は、この長い歴史の中で培われてきた大工中心のものづくり人の世界の上に展開された。そして、建築の近代化は、ものづくり人の活躍する地域や階層の更なる拡張によって成し遂げられていったのだ。もしも十分な数の優れたものづくり人が全国津々浦々に存在していれば、生み出す建築の価値が上昇する形で、日本全体の大小様々な建築の生産性が総じて向上することになる。
ものづくり人の中核である大工の人数を国勢調査で見てみよう。大工人数の統計がとられ始めた1930(昭和5)年の国勢調査では 45万人強。国民約140人あたり一人の大工がいるという状態だった。当時よりも遥かに建築工事量の多い最近の2015(平成27)年に、約359人に一人しか大工がいないという状況であることを考えると、少なくとも戦��前の大工数は、建築の生産性向上を支えるのに十分なものだったと言えそうである。
戦後の日本全国の大工人数を見てみよう。1950年は「大工徒弟」という分類があり、これを合わせると約50万人(約167人に一人の大工)、1955年は約52万人(約170人に一人)、1960年は約61万人(約151人に一人)、1965年は約69万人(約142人に一人)、1970年は約85万人(約122人に一人)、1975年は約87万人(約129人に一人)、1980年は約94万人(約125人に一人)。ここまでは大工人数は右肩上がり、増加の一途を辿っていた。コンクリート工事の要となった型枠大工もこの中に含まれていた。
千年築いた基層が崩れる
ところが、1980年を境に大工数は減少し始める。丁度私が大学院に進んだ年である。1985年は約80万人(約151人に一人)。初めての減少、それも5年で14万人も減ってしまった。続く1990年は約73万人(約168人に一人)、1995年は約76万人(約165人に一人)、2000年は約65万人(約196人に一人)、2005年は約54万人(約237人に一人)、2010(平成 22)年は約40万人(約322人に一人)、2015(平成27)年は約35万人(約359人に一人)という具合である。特に21世紀に入ってからの減少の速さは異常であり、日本のものづくり人の世界が長い年月をかけて形成されてきた過程に思いを馳せる時、切なさとともに大きな危機感を覚えずにはいられない。
ここで、前回の拙稿で文化の基層と申し上げたものづくり人の世界について、危機感を覚える背景をもう少し具体的に把握しておきたい。そうしなければ対策の講じようもない。手掛かりはやはり国勢調査。公表されている中で最新の2015年の数字を��少し詳しく見てみよう。

先ずは大工。何度も言うように日本全体では35万人。その内の5歳刻みの人数が公表されているが、一番多いのは60~64歳で6万人強。65~69歳が5万人弱、55~59歳が4万人強と続く。平均年齢は52.4歳。驚くべきことに、将来を担うであろう15~19歳の大工は3千人を切ってしまっている。全体の1%にも満たず、60歳代前半の大工の20分の1に過ぎないのだ。どうする?ちなみに伝統的な職種である左官は、全体で7万人強、平均年齢は55.9歳。15~19歳の左官は全国でたったの660人とこれまた1%に届かず。和室を支える畳職人に至っては、1万4千人強で平均年齢は57.3歳にもなる。15~19歳の畳職人は僅か50人で、もちろん1%にも遠く及ばない。一体全体、どうするのだ?
建築と都市の危うい基層を救うのは誰か
建築と都市の基層にあるものづくり人の危うさについて、共有して頂けただろうか。建築に関りがあろうとなかろうと、できるだけ多くの人に危機感を共有して頂くことこそが未来への第一歩だと考える。
渡辺保忠先生があの論文を書かれた1960年頃。ものづくり人は増加の一途を辿っていた。職場環境や待遇��、働き方等にさほどの気を遣わなくとも、ものづくり人の世界の門を叩く若者はどんどん増えていたのである。先の数字から見ても、業界全体の慢心は当然起こり得た。1960~1970年代には誰も大工が減るなどとは思ってもいなかっただろう。ところが、1980年代に入って減少が始まり、その時点で平均年齢の上昇傾向も見られるようになった。結構な騒ぎになった。建設業界は「3K(Kiken, Kitanai, Kitsui)」だからこれを解決しなければならないとか、ゼネコンや住宅メーカーが大工を社員化することを検討すべきではないかとか、ロボットを初めとする機械で置き換えることはできないのか等々、色々な取組みテーマが挙がったが、それが40年後の2022年においてもなお、変わらず検討のテーマとして取り上げられているとは思っても見なかった。この40年を振り返ると、取り組むべきテーマが違っていたのではないかとしか考えようがない。
今私が主なテーマに掲げるべきだと思っているのは、「ものづくり人」の楽しみを取り戻し、それを人生に豊かさをもたらすものとして位置付け直すこと。冒頭のスタッズ・ターケルの言葉を借りると、「仕事・ふつうの人のふつう以上の夢」をかなえられる世界にすることである。さしあたり、次回からは夢を持ってものづくり人の世界に飛び込んできた女性たちの生の声を聞いてみたいと思う。スタッズ・ターケルのように深い話を聞き出せるかどうかには自信がないが、まあやってみることにしよう。
*¹ ここからの渡辺保忠さんの著作の要約と大工人数に関する記述は、拙著「21世紀がテーマとすべき生産性-建築分野-」、「コンクリート工学」Vol.55 No.9、848-851頁、コンクリート工学会、2017年9月より引用の上加筆修正したものである。
本文中に登場した書籍
『仕事!』著 スタッズ・ターケル、訳 中山容(晶文社、1983年)
『工業化への道』(不二サッシ、1962年)