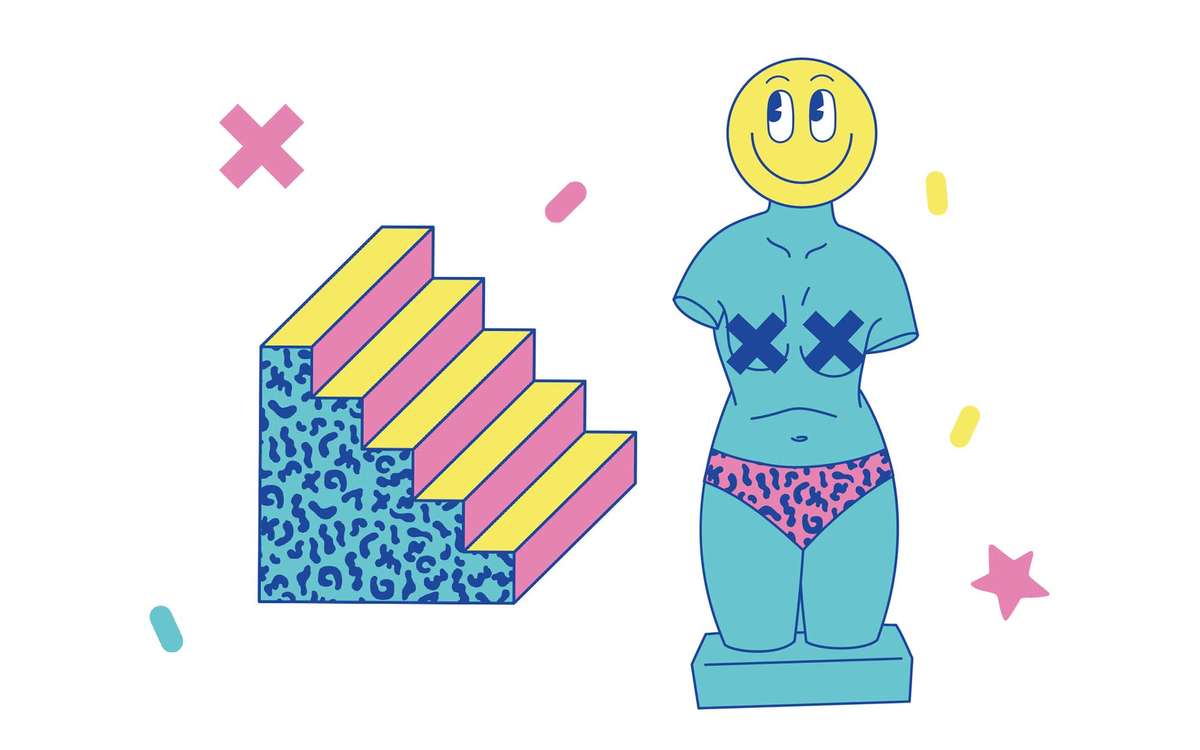死者を隠すということ
死には、公表されるものと秘匿されるものがある。
新型コロナに罹患して亡くなった人のことについては、親戚にさえ言えないという例があった。病気に罹った事自体が過ちのようにとられかねないからだ。あまりに不条理に思われるかもしれないが、実はこのような例は今にはじまったことではない。古くから人類文化には感染症で死んだ人がいる家を忌避する、すなわちケガレ同様に扱う現象がみられる。
一方で第二次世界大戦後には、亡くなった一人ひとりを決して忘れてはいけないという意味で、全ての死者を記して、祈念するという考え方も広まってきた。
沖縄には平和の礎(いしじ)というものがあって、そこには兵士だけではなく住民も含めたたくさんの亡くなった方の名前が記されている。
最近では大きな事件で亡くなった方の名前を報道することが控えられているが、社会が「死者を忘れてはならない」という考え方を持つのならば、弔うために名前を挙げることはむしろ欠かせないことではないだろうか。
隠すことだけが死者の尊厳を守ることではない
一方で、むごい亡くなり方をした家族の名前を公表したくないという遺族には、それを「消費されたくない」という思いがあるのだろう。
例えば、水俣でユージン・スミス(William Eugene Smith)が撮った上村智子(かみむらともこ)さんの有名な写真がある。母親が入浴をさせているシーンで、『水俣母子』というタイトルがつけられた。水俣の悲劇を象徴するものとしてよくポスターなどに刷られため見たことがある方も多いだろう。その後上村さんは21歳で亡くなるが、この写真は、時を経るにつれて新たな局面を迎えていく。
「上村さんのきょうだいが通う教室では、教師が写真を見せて「水俣ではこんな不幸な生まれ方をした人がいた。今後は決してこのようなことを起こしてはいけない」という趣旨の話をしたことがあったという。それに対し、妹は「その写真は私の姉です。姉のことをそんな風に言わないでください」と泣きながら発言した。その教師は、当事者が持つ思いを理解せずに、公害批判教育に取り組んできたつもりだったが、深く反省させられたという(原田正純『宝子たち――胎児性水俣病に学んだ50年』弦書房、2005年、27ページ)。
また、刷られたポスターはときに地面に落ちて人に踏まれることがある。落とした人にしろ踏んだ人にしろ、そこに悪意がないことが多いが、それでも被写体はある種の軽薄な扱いを受ける。それはやはり死者に対する冒涜になってしまう。ユージン・スミスのパートナーであるアイリーンさんはそれに胸を痛め、写真を封印した。それは遺族たちの願いでもあった。

日本では2021年に公開された『MINAMATA』においては各種の調整のうえ、写真を使うことに遺族もアイリーンさんも同意した。そのため、この写真は再び世に出るようになった。映画やそこに映しだされた写真を見て、水俣病とともに生きた人々の人生に思いを巡らせた方もいるのではないか。
死者の名前や生前の姿、情報は現在を生きる人々に大切な問いを投げかけ、悼みの気持ちを起こさせることがある。だからこそ、死者の尊厳を守る方法の一つとして、その名前を挙げるということがふさわしくないと感じる人がいるとすれば、その理由をよく考えなくてはならない。あまりに慎重に扱いすぎるということは、亡くなった方の尊厳を逆に傷つけることもある。
一方で、亡くなった方や家族に対する偏見、差別というものが社会にあるということを、土台にして考えることも必要だ。デジタル社会においては、一度発信された情報は抹消できないのだから。
人間のクローン生成は先送りできない問題
名前だけでなく、死者が持っていた肉体に関する情報の扱いについても、もっともっと議論を深めていかなくてはならないだろう。
AIの進歩により、現代では、記録されている故人の声も生存者の声も新たにコンピューターが生成することができる。そこで生まれたのが、2019年末の紅白歌合戦のAI美空ひばりのようなプロジェクトだ。これらは今生きている人々を喜ばせることができるというメリットがある反面、命の実感を薄れさせてしまうという側面もある。
さらには、情報と生命の操作が繋がり、ゲノム編集により命を操作することもできるようになった。合成生物学のジャンルでは、ゲノム情報から新たな生命体をつくることも行われている。おそらく、命は操作できる情報から成りたっているという感覚が増えているのだ。私はこれを命のリアリティというものが人工的なものによって、代替されようとしているのではないかと考える。
すでに技術面では、亡くなった子どものクローンを作ることもさほど難しくない。だからこそ、人類社会でそれを納得できるのか、その根拠は何なのかをもっと話さなくてはならない。もう先送りにはできない時代なのだ。
コントロールできないことの効用を考えるべき
例えば、アニメのキャラクターを人間さながらに愛してしまう人たちがいる。それ自体を間違っていると断罪することはできないが、人が作ったものをリアルないのちと捉えることには問題がある。��なぜならそれは、人の意思次第でコントロール可能なものだからだ。生きている人間は、例え本人の意思をもってしても、完全にコントロールすることはほとんどできない。そこに命の神秘があり、尊さがある。すべてコントロールされたものばかりを愛することは、科学技術文明の行きつく先の一つの大きな問題なのだ。

命というものは、コントロールできない要素を持っている。だからこそ、人はお互い助け合う。命は自分でコントロールできないということがよくわかっているからこそ、謙虚になれる。デジタル化でいろいろなことが「できる」時代になるからこそ、コントロールできないことの悲しみと恵みに目を向けるべきだ。
自然をコントロールしようとする思想が進んだ背景には、西洋のキリスト教文化がそれに肯定的な方向に進んだことが挙げられる。人間が自然を支配することを、「神が人間に与えた使命」として受け取ったのだ。これが資本主義と結びつき、人間が環境や人体をコントロールすることが幸せに通じるという考えに取り憑かれるようになってしまった。さらには業績主義、市場経済の競争に勝てば、それが善になってしまうような環境ができあがった。
生きているのではなく、生かされている
その結果が、環境破壊や人間自身の生命のコントロールである。このことに違和感を覚える感覚をもっている人は少なくないはずだし、これを一部の宗教が強力に主張しているわけでもないが、私はこの違和感はなにか宗教的なものに通じると感じている。すなわち、コントロールできない何かが人間にとって非常に大切だということだ。
私はこれをよく「いのちの恵み」と表現しているが、コントロールするものからは見えないようなところにこそ命の大切な働きがあるという考え方だ。マイケル・サンデルはこれを”giftedness of life”といった。「贈られたものとしての命」である。これは日本語でいえば「おかげさま」などに通じる。ひいては「もったいない」「いただきます」とか「ごちそうさま」という言葉にも現れる。生きているのではなく、生かされている。命があって、私たちがあるという感覚。それが次第に弱まっていくことに、私は人間の驕りを感じずにはいられない。それが生む結末について環境問題の場合には、やっと見えてきたものがあるが、ゲノムや人体をどう作り変えるかという面については、いまも未知の面がある。というのも、医療は人の命を救うものだという前提がいまだに強くあるので、なかなか医療がもたらすかもしれない危険、危うさが共通認識になっていない。
実は私も、若い頃は「医療とは人の命を救うものだ」という認識があった。しかし1967年の心臓移植、体外受精の1978年、クローン羊の1996年などがあって、生命科�学が恵みとしての命というものをコントロールできる物として作り変えはじめていることに危うさを感じるようになった。生命科学の進歩は人をますます幸せにする、ということを信じすぎてはならないと考えるようになってきたのだ。
技術が何かを便利にするときには、何かを失っていないかという問いが常に必要になるだろう。便利さというものは基本的に誰かの管理の元にあるので、管理されない物は意識から省かれ、軽んじられてしまう。それは文化的な貧しさ、あるいは情感の貧しさ、あるいは心の貧しさというようなところにつながりかねない。