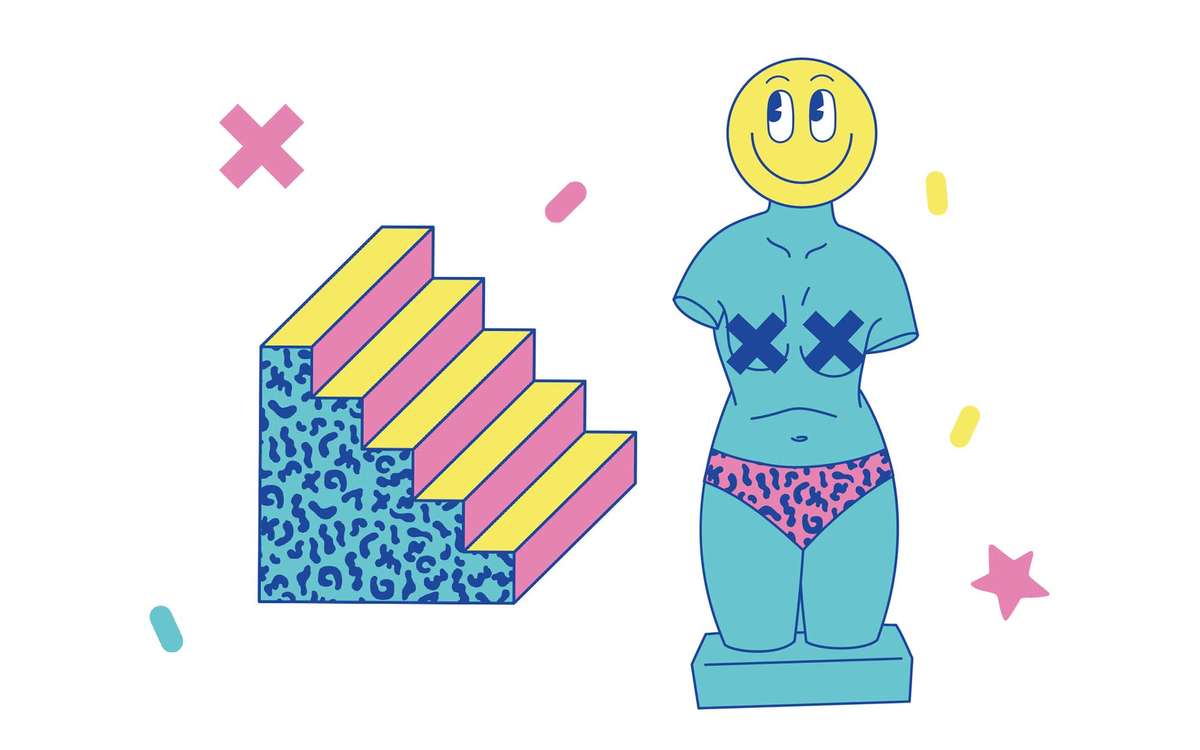大量消費型経済システムの中にある「おすすめ」
先日、自分の「香りタイプ」が分かるというオンライン診断をやってみた。香料メーカーらが開発したAIを用いたシステムで、いくつかの質問に答えていくと、おすすめの香りを教えてくれるというものだ。結果、私は「ハーブタイプ」で、ミントなどのほかムスクがおすすめとのこと。実は私は、ムスクはどちらかというと苦手な香りで、ハーブ系全般も自ら好んで選ぶことはあまりない。だが、「おすすめ」というなら今度試してみようかという気にもなり、そんな自分がマーケティングに乗せられているのではないかと少し悔しくもあった。
こうしたAI技術を用いたいわゆる「レコメンデーション(おすすめ)」サービスは、近年様々な業界でマーケティングの一環として使われるようになった。昨年12月には渋谷の食料品店で、客の好みに合った日本酒の銘柄を提案してくれるAIシステムが試験的に使われた。東京駅や新橋駅などに設置された無人コーヒースタンドでは、AI技術を用いて自分「好み」のコーヒーを選べる試みなどが広がっている。これらのシステムは、AIに商品購入履歴を学習させたり、冒頭の例のように利用者の質問に対する回答から個々人の好みを割り出す。

このような新たなマーケティング戦略は、従来のマスマーケティングを超えた「パーソナルマーケティ�ング」のようにもみえる。一方で、個々の購入履歴や回答を元にしたレコメンデーションサービスは、商品(その味や香りなど)そのものが消費者一人ひとりのためにカスタマイズされるわけでは必ずしもない。多くの商品が市場に溢れるようになったからこそ、個々人の「好み」を特定し、その人に合った(合っているように見える)商品を手軽に提案・提供するサービスの需要が出てきたともいえる。その意味でレコメンデーションサービスは、大量生産・大量消費型経済システムの中にあるものだといえるだろう。
情報の関係性の中から選び出される、現代の「おすすめ」
前回までの論考で述べてきたように、化学産業や感覚科学の発展で感覚に関する様々な研究が進められ、私たちの周りには多種多様の感覚刺激──色や香り、肌触り、味の商品──が溢れるようになった。これにより私たちの感覚体験は以前より豊かになったといえるかもしれない。同時に、情報過多ともいえるこの状況では、何を頼りに商品を選べばよいか分からないことも多いのではないだろうか。これまでは、店員が、レストランでおすすめの料理を教えてくれたり、洋品店では客の体型や好みのスタイルに合わせて商品をすすめてくれたりすることが多かった。現在も実店舗で買い物をする際には店員の役割は小さくない。だがオンラインショッピングが増加しつつある今日、書籍や衣料品、食品など様々なショッピングサイトで、AIを用いたレコメンデーションサービスは、私たちの普段の買い物の一部になりつつある。
AIシステムと店員によるレコメンデーションサービスの大きな違いは、機械と人間という違いのみならず、前者は予測可能性とカテゴリー化を軸に成り立っており、一方、人によるレコメンデーションは、偶発性がその特徴の一つだといえるだろう。例えば香りタイプや好みの日本酒をAIシステムで提案する場合、消費者の嗜好や生活スタイルなどに応じて、その人が好みそうな香りや味を判断するわけだが、そこでは、(嗜好などの)「特性A」を持つ人は「香りB」を好む傾向にあるというように、嗜好・ライフスタイルをカテゴリー化するとともに、それに合わせて香りや味が提案される。つまり、ある特性(A)とある香り(B)との関係はあらかじめ想定(予測)されたもので、その情報の関係性の中で、ある人の好みというものが「診断結果」としてアウトプットされる。
偶発性が生じる、人からの「おすすめ」
一方、店員が何かをすすめる場合、客との対話や買い物をする状況などによって、少なからず偶発的な要因が介入する。客がファッションスタイルの好みを伝える際、AIシステムであれば、提示されるいくつかのスタイルの中から自分に近いものを選ぶことが多いが、相手が店員であれば、自分の好みをかなり細かく伝えたり、逆に、より抽象的に尋ねることも可能である。例えば、服を買う街の雰囲気や着用する目的、春先・初夏・梅雨・晩夏といった本当に微妙な季節感、体調、持ち物との取り合わせや、同行者との相性。その服を着てどう振る舞いたいか。また、「かっこよく見せたい」とか「やわらかい」感じ、のようになんとなく思い描く雰囲気を伝えるなどだ。店員�が出す答えは、そのような個別具体的な状況に埋め込まれた対話にある程度依存する。つまり、店員も買い物客も、事前にある程度こういうものをすすめようとか、こういうものを買いたいという考えがあったとしても、店舗で商品を見たり、話をしたりする過程の中で、予測していたものとは違う商品に行き着くこともある。
また、昔からよく訪れる店で馴染みの店員がいる場合には、ファッションの好みだけでなく、ライフスタイルや性格なども鑑みた上で商品をすすめてくれるだろう。ずっと同じスタイルの服を着ているから今回は少し意外性のあるものを着てみてはどうかというような、従来の購入履歴からは逸脱するような形の提案もあるかもしれない。もちろん、AIシステムにありとあらゆる情報をインプットしたり、購入履歴から逸脱する結果をうまく出すように「学習」させることは可能だろう。だが現状は、マス向けに利用するAIシステムでは調整コストなどの面で現実的ではないだろうし、そもそもAIはそうした偶発性を排することを目的としている側面もあるのではないだろうか。
おすすめは消費者の主体性を奪うものか?
こうしたAIシステムと人間によるレコメンデーションサービスは、どちらがより「正しい」とか、買い手の好みにより合致しているかどうかは一概に判断することはできない。そうした議論自体がナンセンスかもしれない。どちらが「良い」かどうかは、おそらく購入する商品や買い物をするシチュエーション、買い手の好みや何を求めているかなどによって変わるからだ。AIと人間のおすすめが本質的にどのように違い、また似ているのか、それらを理解することで、わたしたち消費者は両者をうまく活用することができるともいえる。AIシステムにせよ人間にせよ、何らかの「おすすめ」を提案してくれることは、自分の好みを(再)発見したり、新しいものを試す機会にも繋がるかもしれない。

また、AIシステムを用いたレコメンデーションサービスによって、人の嗜好やライフスタイルがデータ化され、それらの情報に基づいた「好み」や「タイプ」がおすすめされることは、消費者の主体性が失われるのではないかという議論もあるかもしれない。だが、相手がAIでも店員でも、そのおすすめや自分の好みに関する提案を聞いて、アドバイスに素直に従う場合もあるかもしれないが、「そんなはずはない」と、おすすめされた内容に反発を覚える人もいるかもしれない。その意味では、AIが消費者の主体性を必ずしも奪うことには繋が��らないし、そもそも主体とは様々な人やモノとの関係性の中で生まれるものではないだろうか。
微妙な違いを認識できるようになることとは、新たな世界が作られることである
ブルーノ・ラトゥールが、2004年の論文「How to Talk about the Body」の中で、香水を作る調香師の訓練を例に挙げ、感覚体験と感覚世界がいかに構築されるのかという議論を通して、主体と客体の分離を乗り越えようとする考察を提示している。調香師は様々な香りを嗅ぎ分けるための訓練として、僅かに異なる複数の香りが収められた「香りキット」と呼ばれる道具を使う。一週間にわたるトレーニングセッションを受けた調香師たちは、インストラクターの助言も受けつつ、そのキットの香りを繰り返し嗅ぐことで、微妙な違いを認識できるようになるという。
ここでラトゥールが注目するのは、僅かな香りの違いを認識できるようになったという事実は、単に調香師の嗅覚が敏感になったというだけではなく、彼・彼女らに新しい感覚(嗅覚)世界が作られるということである。つまり、訓練をすることで鼻が微妙な匂いの違いまで嗅ぎ分けられるようになる(身体的変化)と同時に、僅かに異なる数多くの香りが存在する世界(環境的変化)が立ち現れる。そしてこれらは、個々の調香師、インストラクター、香りキットなど、人やモノの関係性の中で生まれるものなのだ。ラトゥールは、主体と客体、そして知覚と現象との境界が溶解し、それによって私たちの�体験が作られていると論じる。新しい感覚に主体(と身体)が「気づく」のではなく、感覚刺激に気づくようになった身体が作られると同時に、(周辺の)感覚世界も作られるのである。
私たちの感覚は、歴史的コンテクストの中で生まれている
レコメンデーションサービスも同様に、自分という人間、AIシステムや店員、商品などの相互作用の中で自分の感覚体験、引いては自分の好みや思考、感性を構築する補助となるといえるだろう。私たち一般消費者の場合、例えばプロの調香師のように特異な嗅覚的能力や、その細かな香りの違いを言葉で言い表す術も持ち合わせていない。その意味で香りなどの感覚刺激を普段それほど意識的に感じたり考えたりしていないのかもしれない。だが、レコメンデーションサービスは、ラトゥールが述べるように、自分の好みや主体、身体やそれを取り巻く感覚世界というものが立ち現れる一つの要因だといえるのではないだろうか。
このようにAIが個々人の嗜好や選択に関わる局面において、主客融合の中で生まれる体験・世界を思い描くことは、機械と人間の関係について新たな見方を提示してくれるかもしれない。この意味で、AIや関連技術について考えることは、人間のあり方について考えることにもつながるといえる。ここで重要なのは、私たちの体験や世界を作り出しているようにみえる様々な人・モノ・技術などは対等に並んでいるわけではないということだ。人と人との関係、多くの人が無自覚のうちに社会に浸透するAIなど、そこにはアンバランスな力関係が見えないところに存在していることも多い。同時に、��こうして作られる感覚体験や感覚世界、身体は、資本主義システムのもとで成り立っており、AI技術の開発を含めて、それらが構築される過程は概して政治的であるということも忘れてはならないだろう。つまり、私たちが体験している世界は、ある特定の歴史的コンテクストの中で生まれたものである。そして、自分の身体、さらには感性や創造性、さらにはそれらを作る一要素となりうる技術や文化的背景は、決してニュートラルなものではなく、その時代・社会における様々なパワーポリティクスと無関係ではないのだ。
参考文献
源河亨『「美味しい」とは何か—食からひもとく美学入門』(中央公論新社 2022年)
長滝祥司『メディアとしての身体—世界/他者と交流するためのインターフェース』(東京大学出版会 2022年)
Latour, Bruno. “How to Talk about the Body: The Normative Dimension of Science Studies.” Body and Society 10 (2–3) (2004): 205–229