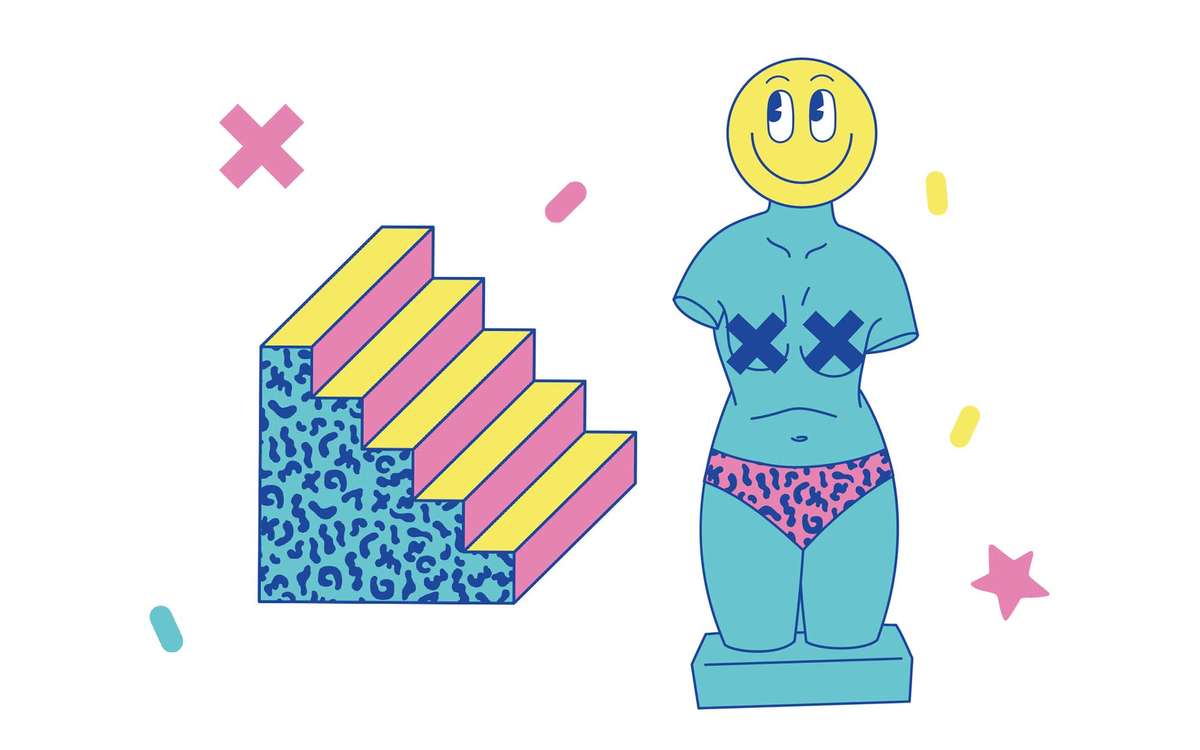資本主義社会が拡大すれば、感覚が鈍化すると考えたマルクス
「君が食べたり飲んだりを少なくすればするほど、そして、本を買ったり劇場や舞踏会や居酒屋に行くのを控えれば控えるほど、また考え、愛し、理論化し、歌い、描き、詩作するのを抑えれば抑えるほど、それだけ君の節約度は高まり、虫にも埃にも侵されない君の宝が、君の資本が、大きくなる。」
これは、カール・マルクスによる『経済学・哲学草稿』(1844年)からの一節である。マルクスといえば言わずと知れた『資本論』等の共著者で、資本主義システムの構造の解明に努めた。そのマルクスにとって、人々(特に労働者)の身体、感覚や感性のあり方は、資本主義社会を分析するにあたり重要な要素の一つであった。マルクスによれば、19世紀半ば以降、資本主義社会が拡大していく中で、人々は資本を増やすために、感性を満たす、または磨くこと—例えば外食や読書、観劇など—をしなくなる。マルクスは、こうした感覚・感性の鈍化を「疎外」の一要因として捉えた。
さらにマルクスは、資本主義システムにおける工業化・機械化に関して、労働者の五感への影響にも注目して論じており、工場では「人工的に高められた温度、原料の屑の充満した空気、耳をろうする騒音などによって、すべての感覚器官は等く傷めつけられる」と述べている。大量生産システムが拡大し、工場労働者が急増していく中で、単純労働を行う人間の身体は機械と化す。そして、高温や悪臭、騒音など工場の劣悪な労働環境は、そこで働く人々の感覚器官にも悪影響を及ぼすものであった。感覚は「すべての学問の土台でなければならない」と論じるマルクスにとって、感覚は、単に外界からの身体刺激であるだけでなく、社会のあり方や人々の生き方そのものでもあったのだ。

こうしたマルクスの感覚・感性、特に資本主義システムにおけるそれらの変化についての考察は、私たちにいくつかの示唆を与えてくれる。もちろん21世紀の私たちの社会は、マルクスが『経済学・哲学草稿』や『資本論』を執筆した時代と大きく異なっており、彼の議論は歴史的コンテクストの中に位置付けて考える必要がある。だが、マルクスの分析は、感覚や感性がいかにその時代・場所・環境によって影響を受けるか、言い換えれば歴史的産物としての感覚・感性という見方を提示してくれる。
もちろんバイオロジカルな感覚器官の働き、例えば視覚や聴覚といった感覚刺激の受動の仕方には大きな変化はないかもしれない。だが、人々が受ける刺激(マルクスの場合には、工場内の騒音や臭いなど)は環境、時代によって異なる。普段の生活を考えてみると、一歩外に出ると自動車の排気ガスの匂いやエンジン音、通りの騒音などで溢れている。だが、自動車がさほど普及していなかった100年前の社会では、街を歩くと今とは全く違った匂いや音がしたはずである。さらに、たとえ同じ匂いや音であったとしても、時代や場所に特有の形で人々に認識されるこ�ともあった。たとえば、今では騒音だと捉える人が多いかもしれないが、大陸横断鉄道が敷設され始めた19世紀末のアメリカにおいては、列車の汽笛音は「モダン」な音であり、技術革新の象徴として受け入れられていた。
このように、五感を歴史的に捉えることは、人々が生きる環境がどのように変化してきたのか、そしてその環境の変化を人々がどのように認識し理解していたのかを包括的に考えることである。つまり、感覚の歴史は、存在論および認識論とも深く関わる問題でもある。身体は物理的な「モノ」として在るだけでなく、文化的なものでもあり、その物理的・文化的構築物としての身体を通して人々は周辺環境を認識する。これは、外界の刺激を受け取る感覚器官(身体)も、それらの刺激の認識の仕方も歴史的に構築されたものとして理解することによって、身体と認識、さらには主体と客体を包括的に捉え、人がある時代・ある場所に生きていることの意味を考えることにもつながるのだ。
資本主義システムが作り出した、新たな感覚世界
ここでもう少しマルクスの感覚についての議論を広げて、現代社会の、特に消費社会との関連で考えてみたい。マルクスの主な関心は、機械化など資本主義下における生産体制と労働者への影響だった。一方、マルクスに続く批評家・研究者、例えばソースティン・ヴェブレンやヴァルター・ベンヤミン、テオドール・アドルノらは、マルクスの影響を受けつつも、視覚や聴覚など五感への影響を含め消費活動の心理的・身体的変化に注目した。そして、資本家(および後に「マスコンシューマー」と呼ばれることになる人々)は、貯蓄のためだけに読書や観劇などを控えて感覚や感性に関わる体験が乏しくなったというよりは、むしろ新しく作り出された五感世界を楽しみ、享受するようになったことを示唆している。そうした新たな感覚世界は、まさに資本主義システムが作り出したものでもあった。
19世紀末から20世紀前半にかけて、大量生産体制の確立や消費主義社会の拡大に伴い、色とりどりの衣服、新たに開発された人工香料が使われた香水や化粧品、多様なデザインの自動車など様々な消費財が人々の生活に溢れるようになった。こうして人工的に作り出された色や匂い、味などは、モノの品質判断基準や消費のあり方を大きく変化させた。さらに、デパートなど新たな商業施設や販売形態が誕生したことで、多種多様の商品が多くの人々の手に届くようにもなった。このような五感に訴える商品開発や技術開発を行う産業・研究機関・政府などが一体となったシステム(産学官複合体)を、科学史家のスティーブン・シェイピンは「感覚産業複合体」と呼んだ*。技術革新と大量生産・大量消費を特徴とす��る資本主義経済のもとで、消費者の感覚すらも企業の生産・マーケティング戦略の中に取り入れられるようになったのである。
*英語では「エステティック・インダストリアル・コンプレックス(aesthetic industrial complex)」
香料メーカーが生み出した新しい「自然」
新しく開発された商品や販売手法は、単に新しいマーケティング戦略の誕生を意味していただけではない。消費者の購買行動や嗜好の変化を促すとともに、人々の五感の感じ方や感覚を通した周辺環境の認知の仕方にも多大な影響を与えたのである。例えば美容産業では、19世紀に香料メーカーがラベンダーやローズなどの香りを化学生成により生み出し、同じ香りの大量生産が可能となった。これら自然(植物)を模倣した商品が消費者の日常生活に定着することで、何を「自然な」ものと認識するかが大きく変化した。技術・資本・市場を供給する資本主義システムの中で生み出された感覚世界。言い換えれば、新しい感覚経験のあり方を生み出すことは、資本主義システムの存続に不可欠な要素として機能するようになったとも言えるだろう。

科学技術の発達で、感性は豊かになったのか?
こうした科学技術の発達、化学産業の発展、資本主義社会の拡大によって生み出された感覚世界について、ドイツの哲学者ヴォルフガング・ヴェルシュは、近代以降「感性化がまさに巨大な無感性化へと転化している」と評した。つまり、資本主義システムの元で生み出された感覚の多様化は、一見「感性化」のようでありながら、実のところ「無感性化」なのだという。例えば、「ポスト近代風」の「美容整形」が施されたショッピング施設や周辺地域では、「膨大な感性化、消費をかきたてる感性化が、生起」している。だが、「洗練された刺激やたくみな演出にもかかわらず、けっきょくまた生じてくるのは、やはり単調さ、退屈でしかない」とヴェルシュは述べる。ヴェルシュにとって、五感に訴え、感覚経験を豊かにするはずの多種多様な刺激は、資本主義社会の中で、空虚な、表面的なものでしかないのだ。それは人々の感覚・感性が、(マルクスとは違った意味で)鈍化—つまり彼の言う「無感性化」—につながるものであった。そして、無限の色や匂い、味など、あまりに多くの刺激に溢れた消費主義社会においては、人々は強い刺激に慣れてしまい感覚が「麻痺」してしまうのだ。
たしかに、大量生産された数々の商品、そこから受けるさまざまな感覚刺激は、消費者の五感や感情に訴え消費を促進するための表層的なもので、私たちの五感は、多過ぎる刺激によって麻痺しつつあると言えるかもしれない。だが、こうした見方は、過去を理想化し、ある意味で現代社会を見る目を曇らせてしまう恐れもある。もし過去の豊かな五感経験が失われつつあるのだとしたら、逆に現代社会だからこそ生まれた新しい感覚というものもあるかもしれない。五感を通して見えてくるもの—社会の変化やその中で紡ぎ出される人々の関係や生き方—は、より一層複雑化する世界の中で、社会のあり方を考えるヒントを与えてくれるのではないだろうか。
参考文献
『経済学・哲学草稿』カール・マルクス 長谷川宏訳(光文社、2010年)
『新版 資本論 第3分冊』カール・マルクス 日本共産党中央委員会社会科学研究所監修(新日本出版社、2020年)
『感性の思考』ヴォルフガング・ヴェルシュ 小林信之訳(勁草書房、1998年)
Steven Shapin(2012) “The Sciences of Subjectivity,” Social Studies of Science 42 (2)
Susan Buck-Morss(1992)“Aesthetic and Anaesthetics: Walter Benjamin’s Artwork Essay Reconsidered”