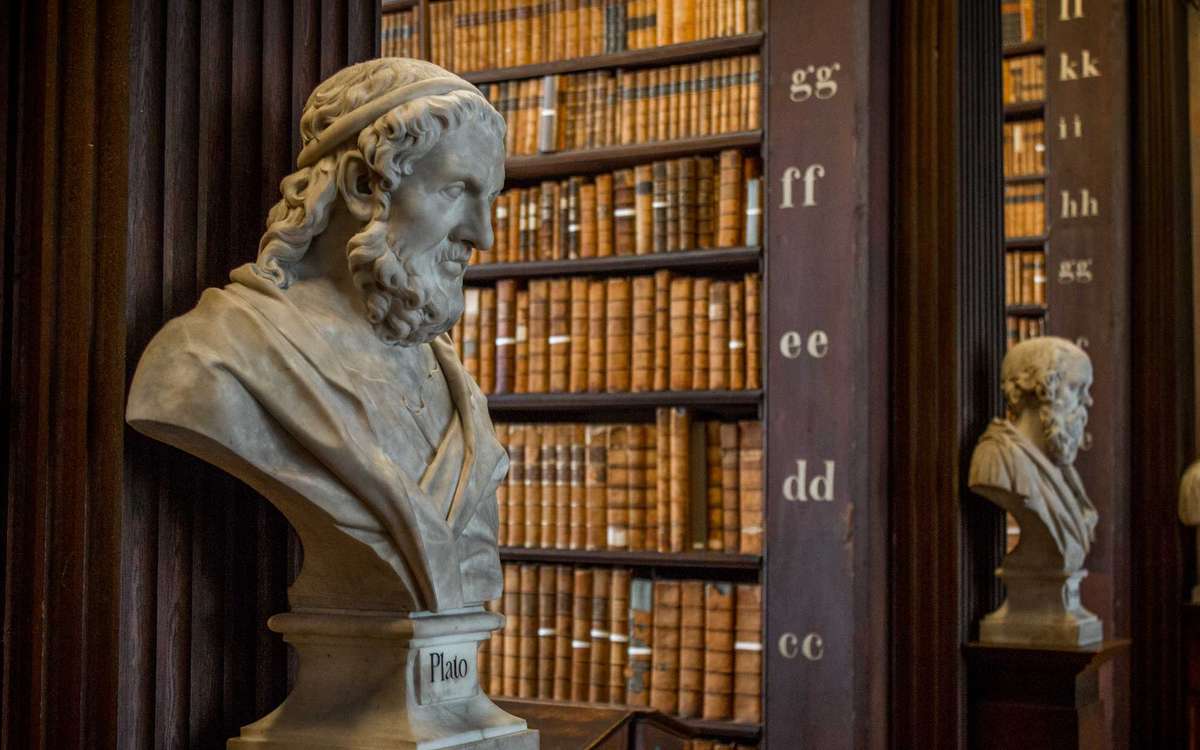科学は始まって1世紀
現在、私たちが評価しているような科学とは、19世紀の�終わりから20世紀初頭ぐらいから本格的に稼働し始めた。例えば、ニュートンは確かに科学的な内容のことを発見してきたが、彼の実績が果たして私たちが今考えるような科学に当てはまるかというと、少なくとも私ははっきり「ノー」だと言う。
それには様々な理由があるが、一つは現代の制度化された科学の外にあるからだ。社会制度として確立された科学というのは、おそらく19世紀の半ば過ぎあたりから、ヨーロッパやアメリカで始まった。日本もご多分に漏れず、それを受け入れている。しかし戦前の科学はまだ本格的な制度活動になっていたとは言えない。制度化が何かを非常にわかりやすいところを捕まえていえば「研究成果は必ず論文誌に論文という形で発表すること」だ。だから私は「科学者の定義は何ですか」と問われると「一番わかりやすいのは論文を書く人だ」と答える。科学の世界では一般に売れる本を書いても何の意味もない。科学者はその仲間つまり自分と同業の人に評価をされることが非常に重要な人々だ。しかも、その同業は日にち毎日狭くなり、どんどん「専門化」していっている。
20年ぐらい前にとある循環器系の医者に会って「先生は循環器の専門家でいらっしゃるそうで」と言ったら「違います」と言われた。では「血管系か、心臓の方ですか」と訊ねたらまた違いますと。では何の専門家なのかと問うと「心臓の僧帽弁だ」とおっしゃった。それくらい研究の現場は専門化している。
『ヘラクレイトスの火―自然科学者の回想的文明批判』という本を書いたE.シャルガフという科学者はノーベル賞を貰い損なった科学者のリストの筆頭にあがる人物だが、そのシャルガフが実に皮肉たっぷりに言っているのが「最近の科学者は、ムカデのX対目の足について研究している」と。私はムカデの足がいくつあるのかは知らないが、日本語では百足と書くから百本は足があるとすれば、その内の一対だけの専門。シャルガフは現代の科学はそういう学問になってしまったと指摘している。
専門知を進歩させるSomething New-ism
そのような狭い狭い専門のなかで採択されるのが論文だ。さらに論文というのはレフェリーに採択されなければ価値をなさない。私は国際的なレフェリーを何度も務めたことがあるが、レフェリーは、普通はチェックリストを持ち、そこにはタイトルは適切か、使われている英語はわかりやすいかなどという、形式的項目が並び、それに照らし合わせて最初の判断をすることが要求される。その上で、内容に関して「あなたはこれをどう評価するか」が問われる。五つ星なのか四つ星なのか。つまり「全く問題なく、載せてよろしい」「多少の手直しが必要」から、「大規模に直す必要あり」「全く駄目」、大体そのくらいにカテゴライズして評価することになる。さらに、小幅な直しならどういうところをどう直すのか。大幅に直さなくてはならない場合はどこが問題で、削除をした方がいい箇所、就く加えるべき内容などもレフェリーは示さなくてはならない。「文句なく駄目」な場合には「ここが駄目だからどうしようもない」と書かなくてはならない。それがいわゆる「リジェクト」だ。
論文を掲載する際の最大の基準は何かというと、Something New-ismに照らし合わせる。これは私の発明でもなければ誰しもが用い�る言葉でもないが、その専門の中で既に研究者のみんなが持っている知識にSomething Newを付け加えるものだったら、良い論文として採択されるということである。そういう考え方をSomething New-ismと呼ぶ。ある学問の塊にSomething Newが少しずつ足されていくことによって、その知識体は大きくなる。そういう意味で言えば、科学は一直線に進歩しているといえるだろう。現行の制度ではそういうことになっている。