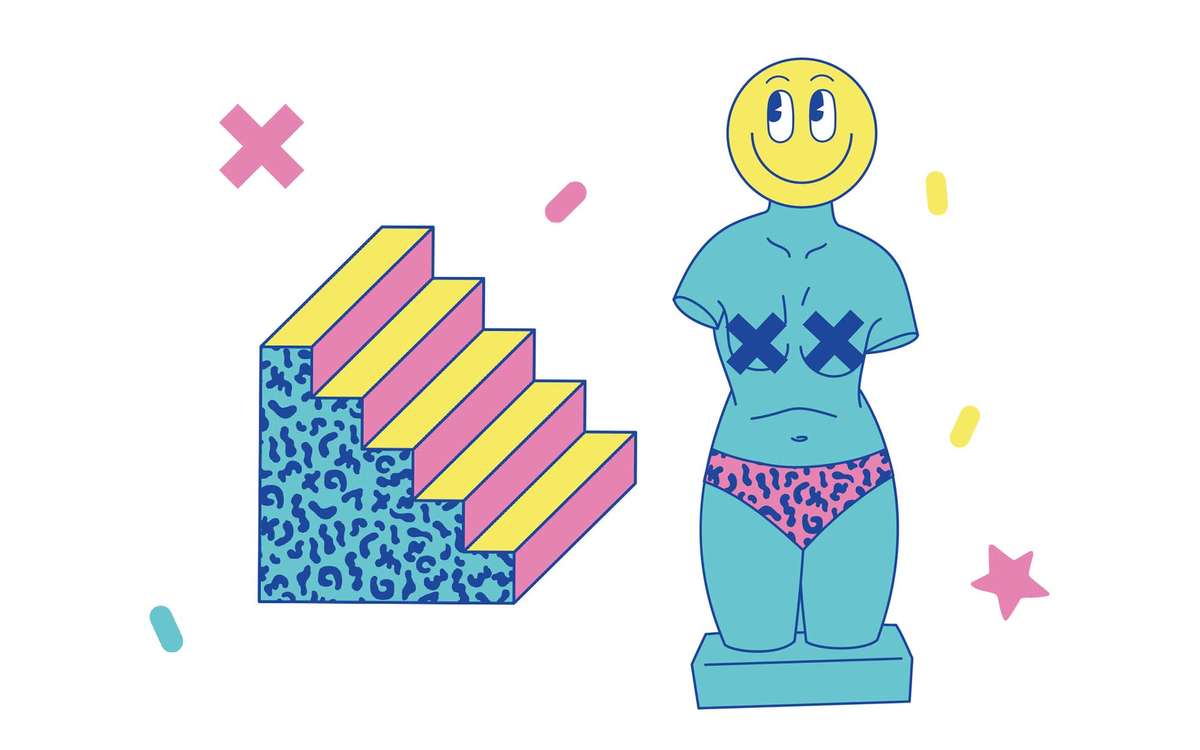生死の境目があやふやな「あいまいな喪失」
近年、「あいまいな喪失」が注目されている。「さようならのない別れ」も関わりが深い現象だ。人が生きているのか死んでいるのかを認識しにくいという経験とも言える。あいまいな喪失はアメリカの臨床心理学者のポーリン・ボス(Pauline Boss)が研究を重ねており、国内では柳田邦男氏がこの現象に注目し言及している。
あいまいな喪失が発生する要因の一つは認知症である。近親者が認知症を患うと、身体はあるけれどもコミュニケーション��ができない、もしくはいくら話してもそれに対する反応が得られないということが起きる。その後老衰などで亡くなったとしても、送り出した側としては生前から亡くなっていたのと同じだったと感じることがあるのだ。
さらにここにきて新型コロナの蔓延により、新たなあいまいな別れの要因が生じた。高齢者が老後を過ごす施設や病院に入って反応が乏しくなっている場合でも、自由に会いにいけるころであればささやかでも反応が得られることは少なくなかったはずだ。ほとんど反応がない、もちろん喋ることもできない状態であっても時々ちらっと表情が緩む。それによって人と人との関係は続いていた。しかし新型コロナが広まったことにより直接会うことが難しくなった。タブレットなどでやりとりができる場合でも、言語ばかりのコミュニケーションが中心になると、反応が得にくい人との関係はもはや保てなくなってしまう。
他方で、行方不明のような、死んだかどうかわからないような別れもあいまいな喪失の異なる形だ。近親者は「もう何年も帰ってこないが、どこかで生きているのかもしれない。しかし、やはり亡くなったのだろうか」という思いを持ち続けることになる。
東日本大震災により未だ2000名以上が行方不明である。残された家族は生死の区切りが見つからず10年以上経った今でも遺骨を探している人もいる。同様のことは9.11のときの米国でも見受けられ、「あの建物の中に、私の大事な人はいたのかしら。もしかしたらいなかったかもしれない。だけど連絡が今でも取れない」という人が何人もいた。

戦争で家族を失くした人たちがなんとか遺骨を拾いにいこうとしたのは、お骨をもって弔いをすることが当時の標準だったからだ。これは特に日本人がこだわってきた死生観の一つである。だから戦後何十年経っても、お骨を拾いにいく人がいた。
ところがだんだんとその標準が崩れてきて、お葬式もしない、あるいは遠くにいるからお葬式に出ようがないと考えるような例が増えてきている。弔いは骨がある場所で一堂に会するのではなく、連絡によってそれを「知る」ことにとどまることが多くなっている。