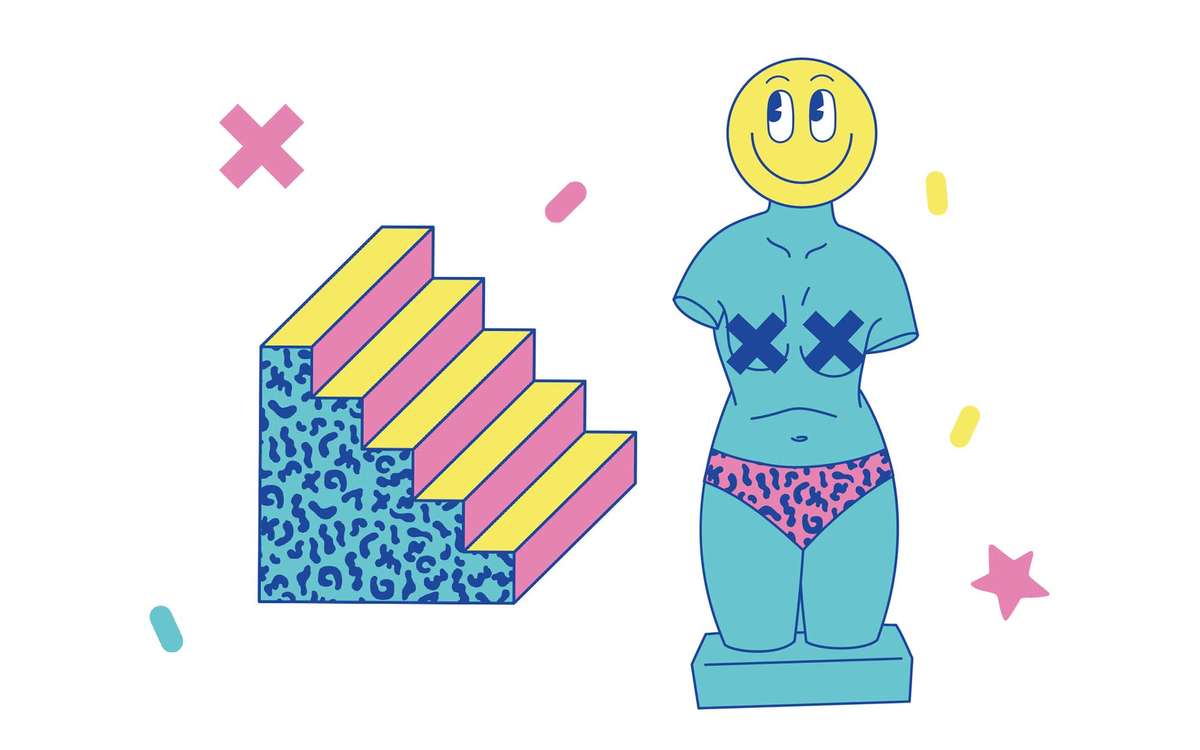「あいまいな喪失」はデジタル化との関係も深い
このあいまいな喪失の感覚というのは、バーチャルな世界とリアルな世界が重なり合っている現代社会のあり方とも関連が深い。例えば、私自身も加齢のせいか付き合いがあった人の生死を忘れてしまうことがしばしばある。最近では新型コロナの影響で葬儀に出ることが難しくなり、ご遺族から「家族だけでお葬式をしました。ご生前には大変お世話になりました」といったメールだけで知らされることも少なくない。訃報は記録にはあるが、記憶にはどうにも残りにくくつい忘れてしまうのである。きちんと葬儀に参列して別れを経験した場合にはあまり起こり得ないことだ。
喪失それ自体は存在するが、喪失を喪失として受け止める装置や、喪失を皆で確認するその機会が失われているのだ。
バーチャルとリアルの境界がなくなるということについては、あえて亡くなった人にメールを送り続けるという行為をする人のことも取り上げられるようになった。「応答のないメール」を送ることで死者との関係を持ち続けているのだ。
ある意味では、これは死者との絆が切れずにいつまでも続いているこ��とを確認しやすい社会になったといえる。しかし逆から見てみると、例え生きていても、連絡を取らなければ死んでいるのと同じことになってしまうのかもしれない。
対面で会うことの少ない現代は、人と人との絆がデジタルに依存する要素が大きい。LINEがあるとか、メールが来ているとか、Facebookで発言していることが存在の証明になっていることもある。そこでの発言が少なくなったなと思ったら実は亡くなっていたということも実際に増えているのではないだろうか。
そこで生じる問題の一つは、自分が社会の堅固なつながりの中に生きているという安定感を得にくいことだと思う。私はそれを「絆がか細くなっている」と表現している。
心の支えにはなりにくいデジタル上の人間関係
日本人のスマホのなかにはどれだけ友人・知人のデータがあるだろう。LINEやFacebookの「友だち」、Twitterのフォロワー、それらは何千人、何万人とつながっている人も少なくない。しかし自分が死んだときに深い喪失を感じてくれる人や、大変なときにすぐに連絡しなければならないほど大事な人は、実はとても少ないのではないだろうか。
現代はそもそも兄弟や親戚の数が多くない。さらに親・兄弟であってもほとんど連絡をとらない人もいる。配偶者がいない人も少なくない。孤立・孤独というのはごく身近にある現象になっている。
だからこそリアルで大事な人との関係の比重が非常に大きくなる。それだけにその関係の喪失は危機的なものとなるのだ。すると、亡くなったとしても近親者にとって故人との関係は重要であり続ける。これまでその方が自分の人生にとって持っていた重みが簡単にはなくならず、いつまでもその重みを抱えていくことになる。それに代わる新しい繋がりはそう簡単にできるものではないからだ。
このことは現代人の死生観にかなり大きな影響を与えている。死別が持つ意味がこれまで以上に大きくなり、死者とともにいることも重視されるようになった。
元来、人と人との関係というのはもろく崩れやすいものだ。しかしかつては張り巡らされた網のような関係がそこに関わっていたから、そう簡単に繋がりがなくなってしまうことはなかった。一つひとつの関係が細かったとしてもそれらは束状に太く補強されていた。だから、いずれかの関係の糸が切れたとしても人との繋がりは残る。もともと、昔の葬式にはそのような切れた分の関係を補強するような意味があった。

人間関係がデジタルに依存するようになると、たくさんの関係を持っているようでいて実はその多くは人の支えにはならない。デジタル化による社会の変化は、死生観への関心を変えていくだろう。人は従来よりも孤独になり、その分、自分の死や他者の死についてもより意識せざるを得ない。