大正教養主義、旧制高校、漱石
ここまではエリートの原点とでも言うべき論点を考えてみました。次は、教養ということになりますが、これは一筋縄ではいかない。そもそも「教養」という熟語は、漢語としてはすでに『後漢書』に現れると言いますが、文字通り「教え育てる」ことの意でありました。近代日本の文章の中では、クリスチャンであり、かつ社会主義的な活動家であり、かつまた作家でもあった木下尚江(一八六九〜一九三七)の『良人の自白』と いう長編小説(明治三十八年刊)の中で、主人公の弁護士が、ある事情で引き取った子供を、「君の子供として教養してくれ」と妻に言う表現に出会うことができます。明治二十四年版の『大言海』(大槻文彦著)には、そもそもエントリーがありません。つまり明治年間には、今のような意味での「教養」の使い方は、ほとんど見当たらない、と考えてよさそうです。
そこで誰もが注目するのが、大正教養主義のリーダーとも言うべき阿部次郎(一八八三〜一九五九)ということになります。阿部は一高で荻原井泉水(一八八四〜一九七六)、 岩波茂�雄(一八八一〜一九四六)、斎藤茂吉(一八八二〜一九五三)らと交わり、帝国大学卒業後は、漱石の門人として、小宮豊隆(一八八四〜一九六六)、森田草平(一八八一〜 一九四九)、和辻哲郎(一八八九〜一九六〇)らとも交流があった人物です。その彼が大正三年に発表した『三太郎の日記』は、当時の中学・高校生必読の書となりました。あるいは、彼らとはかなり異なった系統の人物ではありますが、倉田百三(一八九一〜一九四三)の『愛と認識との出発』(大正十年刊、ただしその一部となる論考は大正二年、一高に在学中に文芸機関誌に発表、物議を醸しました)なども、その部類かもしれません (戦後に角川書店が発刊した「日本教養全集」の第一巻に、上の二作品が収められています)。 ここに挙げた「文化人」、あるいは「教養人」たちの思想が、良くも悪くも、その後の日本における「教養」という概念を決定づけた、と考えられます。土田杏村(一八九一〜一九三四)の名も忘れるべきではないかもしれません。土田は上に挙げた人々ほど世に知られていいないかもしれませんが、後発の京都帝国大学の出身で、独特の文化運動に挺身した人物です。
彼らの思想の基礎は、十八世紀から十九世紀ドイツの哲学者、つまりカント、ショーペンハウアー、ニーチェら、それに阿部にとって重要だったのは、同じ時期のドイツ語圏で形成されつつあった芸術という概念に纏わる「美学」(例えばヘーゲル)にありました。実際『三太郎�の日記』は、ドイツ語、ドイツの哲学者、美学者の名前で溢れていま す。「アンビション」(ambition = 向上心、名誉心)や「アスピレーション」(aspiration = 野望、大志)など偶に英語も現れますが、「エアレーベン」(erleben = 体得する)だとか 「エアファーレン」(erfahren = 経験する)、「ヴェルトゲフュール」(Weltgefuehl = 世界の中で生きているという実感)、「レーベンスゲフュール」(Lebensgefuehl = 生きているという感覚)だの、ドイツ語で満杯です。そしてもう一つ目立つのはドストイェフスキー、トルストイら、ロシアの高踏派の文芸が、繰り返し論じられます。このようなカタカナ語で埋め尽くされている書物を、「普通の」人々が読めたはずはありません。つまり、こうした種類の読書は、旧制高等学校から大学生という、当時の総人口からすれば微々たる数の、特権的場所にいる男性たちの、自慰行為に等しいものであったとも言えましょう。それが「教養」であるならば、やはり教養は、鼻持ちならない臭みを帯びた概念になっても仕方がない、とも言えるでしょうか。
さらに、ドイツ近代「テツガク」への傾倒の裏返しで、彼らは、例えば歌舞伎に代表されるような、日本の江戸期の伝統芸能に、芸術的な「美」を求めることを拒否しました。ドイツ哲学を中心とした書物と学識を通じての人格の陶冶と、高尚な美の追究、禁欲的で、抑制的な人間性を磨くことにこそ、「教養」の本質がある、とみなしたのです。 もう一つその裏では、そうした旧制高校生たちは、内心軽蔑する三業地へ出入りをすることも、結構習慣化していたようで、そうした際の女性は、劣情を満足させてくれる道具のように見られていたようでもありました。その点で、彼らの師の一人となった夏目漱石は、少し肌合いが違います。
たしかに漱石には、『それから』の代助や、『行人』の一郎や二郎のように、いわゆる インテリの人間的な苦悩(それこそ、阿部次郎なら「レーベンスシュメルツ」とでも書いた かもしれません)や、現実の卑俗性への冷たい眼差しが感じられる人物像が描かれます (別のところでも書きましたが、一高寮歌『嗚呼玉杯に花受けて』には「栄華の巷低く見て」 という言葉が見えます)。しかし、よく知られているように、漱石には強い江戸趣味もり、三代目小さんの芸には感嘆を惜しみません。『猫』には、インテリ性と庶民性とがない交ぜになっていますし、あるいは『坑夫』のように、非インテリの世界にも、介入することを躊躇わないところがあります。さらに言えば、漱石の描く世界には、エリートや知識層の持つ精神的、あるいは実生活上の脆弱さと対比された、非エリート層の人々が、はっきりした存在感をもって描かれます。『門』における「安井」や、『明暗』 における「小林」などが、それに当りましょう。彼らの前に、エリートたちは、どこか不安げで、しかも、その点が見透かされているような印象を与えます。『坊ちゃん』は、この構図を逆転させた試みとも取れるかもしれません。もっともそれは、『猫』や『坊ちゃん』は別にしても、漱石がもっぱら朝日新聞という、新聞の一般読者を相手にしていたから、という面も否定できないでしょうが。
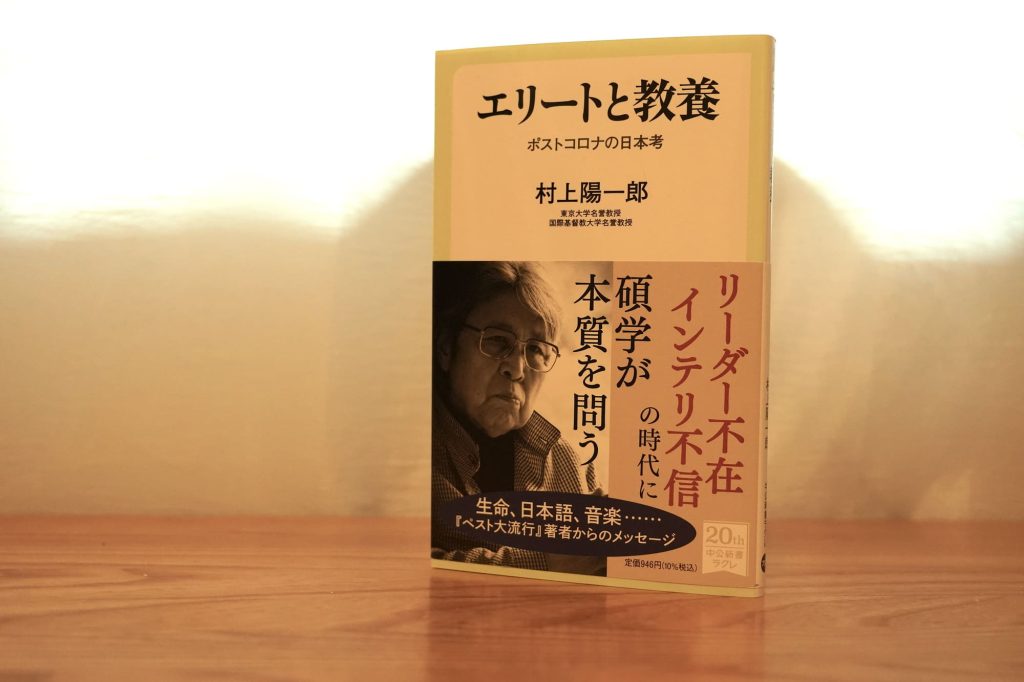
この記事は2022年2月に発行された『エリートと教養 ポストコロナの日本考』(村上陽一郎 中公新書ラクレ)より本文の一部を抜き出して掲載しています。
2022年2月18日(金)にはオンラインにて村上陽一郎氏による本刊行記念特別講義を開催。くわしくはこちらよりご確認ください。








