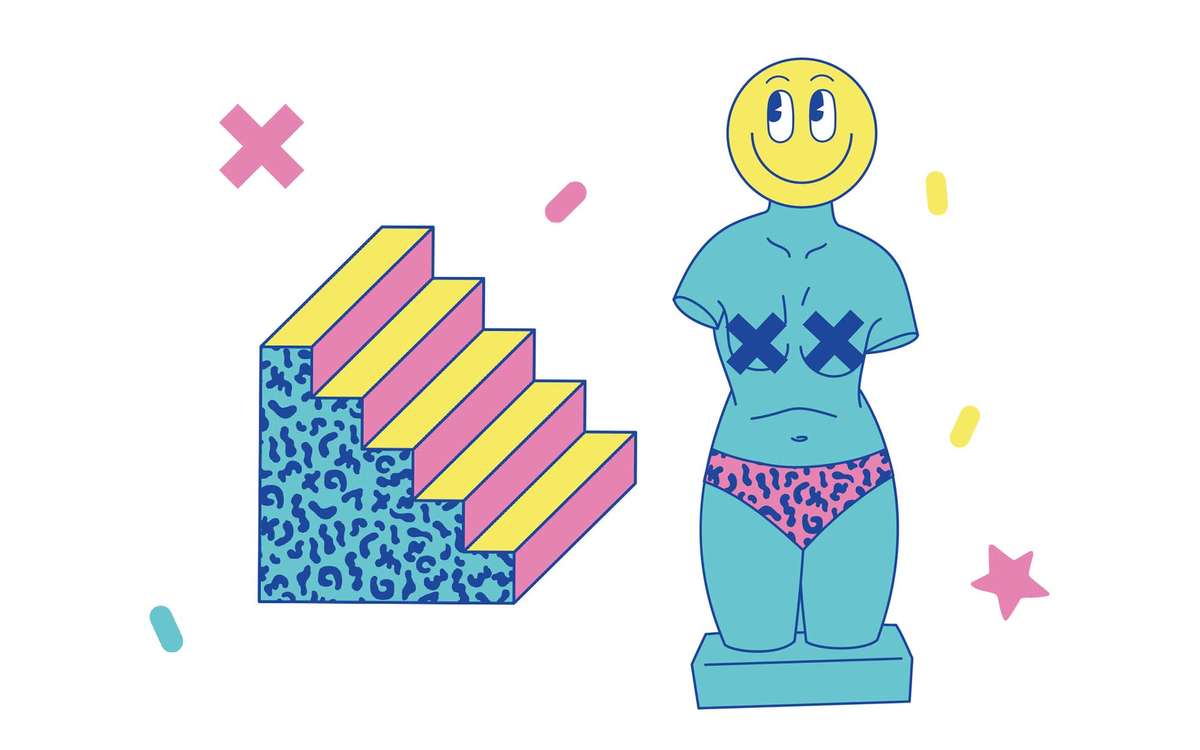死者の「その後」を決めることは古くから見られる文化
実は、生者が死者の「その後」を決める思想というのは今に生まれたものではなく、とくに東アジアの文化圏では古くから見られる。
その一つの例が冥婚だ。韓国や中国、そして日本の一部地域で行われる冥婚は、亡くなった人をあの世で結婚させる儀式である。日本の東北地方には同様の供養としてムカサリ絵馬というものが奉納されている。ムカサリ絵馬は死んだ子供が成人するはずの頃に、結婚相手をみつけて縁談をとりつけ、結婚式の絵を描いて神社に納めるものだ。男の子の家族が行うケースが多いが、女の子の花婿探しも行われる。

そのほかにもあの世であたかも生きているように想像する文化は東アジアに少なくない。死者の世界がリアルに存在するように語られることもある。例えば、東北地方の地蔵盆に行われる「仏降ろし」もその一種といえる。「仏降ろし」は口寄せの一種で、訓練を受けた盲目の女性・イタコに死者を憑依させる。遺された人々はイタコを通じて死者の言葉を聞いた。
このような発想が生まれた背景には儒教の影響があるだろう。死者を先祖として大事にするという伝統のなかで、「誰かの先祖になれない死者」をどうするのかと考えたときに、このような供養が発生したのではないか。
死後の世界をリアルに語る文化は、東アジアのほかには古代エジプトやアフリカの一部にもみられる。
増える「死者との交流」
時代の統治者を特別な棺に入れて葬ることは多くの文化圏で見られることから、死後の魂の存続、死者と生者がやりとりするという文化自体は珍しいものではなかったと考えられる。
そもそも人類文化では死者を葬ることは、こと古代において大事だった。だからこそ、ピラミッドや中国の兵馬俑の入った墓、日本の古墳といった大掛かりな墓作りが行われたのだ。しかしそれは社会の文明化とともに世界的には薄らいでいった。特にキリスト教、イスラム教、仏教では死者と生者��と直接やりとりすることは、基本的には正しい信仰とはみなされなかったため、それらが色濃く介入した文化圏では死者との関係を築くものはいっそう早く立ち消えていった。
ところが現在のようにデジタル文化が広まり、伝統的な宗教の信仰の影響が弱まってきている中では、死者とやりとりするということは特別なことではなくなってきている。長い目で見ると死者との関係が復活してきているといえるかもしれない。世界全体を全知全能で支配する神の存在がイメージしにくくなったかわりに、身近な死者の存在を人々が受け入れていくような傾向が見られる。
もともと、死者が夢に出てくるという経験をする人は昔から少なくない。日本人には死が近づいてくると前に死んだ人が夢枕に出てくるという経験をしたり、あるいは白昼夢というか、眠っているわけではないのに非実在のものの声を聞くという経験をしたりする人が随分と前からいたようである。生の現実ではない世界との交流が、ある程度のリアリティを持って受け止められる文化があったのだ。それが一層、死者の存在感を感じやすいものにしている。このような経験はデジタル的な空間とシンクロする面があるのではないだろうか。