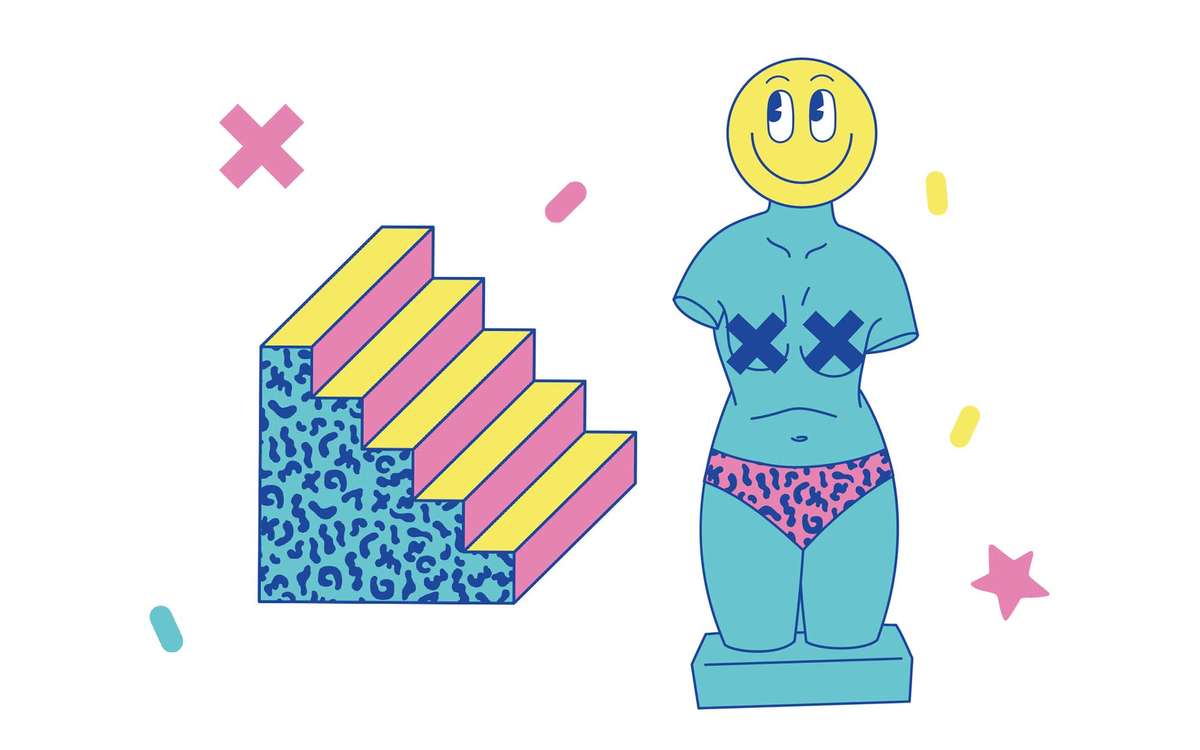魂の行き先を誰が決めるのか
呼吸や血流が止まると生命の全てが終わる、その人は無に帰すると考える人は今の西洋社会では少なくない。しかし一方で、神を信じる人の数以上にこの世の命を超えて命は続くという考え方の人はいる。
よく抱かれる死後のイメージには、天国へ昇っていくという考えのほか、輪廻転生や宮沢賢治のように宇宙の塵になるといったものがある。志賀直哉は「ナイルの水の一滴」のなかで人の命は大河の一滴のようなものだと書いた。つまり、死後にいのちが続くと考える人のなかでもそのイメージは多様なのである。
だからこそ残された肉体の扱いも様々であるといえる。最近では散骨や樹木葬が人気を集めているという。大地の中に入って地球環境の中に蘇ってくるという思想があるのだろう。「いのちはこれっきりではない」という思いが根底にあるのだ。実はこれはかねていわれてきた「神様の御許に召される」や「大自然の懐に還る」という発想に通じている。前者は西洋のキリスト教風な言い方で、後者は日本風の表現だ。特に信仰を持たない人であっても「土に還る」とか「大地の懐に帰る」とかいう表現には親しみを感じるかもしれない。
「無に帰す」というのは、元々は無なのだという考え方だ。人��間という元々堅固なリアリティはないんだという発想で、そこから「空」や「無」という理念がでてくる。これは仏教的な発想だ。死んだからといって全然違う状態になるわけではなく、同じような現象の寄り集まりとして存在していた人間が、また死後も別の形で続いていくという考えだ。
このように「いのち」は肉体的な死によって終わるというわけではないという考え方はかなり広い文化圏に見られる。
ここで私が指摘したいのは、古来、人の「死後」を残された人々が構築していく例は少なくないということだ。とりわけ悲惨な死をとげた人たちは、死後に大きな働きを負わされることがある。故人の死を政治的に利用されることは、死の意味を取り違えていると受けとめる人もいるだろう。そのために死後の扱いを巡って遺族間で争いが起きることは昔からよくある。「共に悼む」という行為は簡単ではないのだ。

死後に遺族に無用な争いを遺さぬためには、弔いの方法まで事細かに記した遺書を用意すべきかもしれない。死んだ後に自分を勝手に復元されないようにするために、意思表示しておかなくてはならない時代が来るかもしれない。人間はそこまで死後のことを考えなくてはならないのかとやや面倒な気持ちになる。
別に、デジタルに頼らずとも故人の部屋や思い出の品をずっと大切にする、記念の場所に訪れることで思い出に浸るということもできる。もちろんお墓参りに行けばそこであたかも言葉を交わすような気持ちになる。そこに別にデジタルが介入する必要はないように感じる。だが、技術を用いだすとなかなか手放せなくなるのも事実だ。
また家族や友人だけでなく、ペットの死後の扱いも変わってきていると聞く。ペットは人格権のようなものを鑑みられることが少ないため、人間よりも容易に「復元」が試みられてきたし、最近ではクローンが作られたという話もある。しかしこの問題の本質はペットロスへの対処方法ではない。そもそもの問題は、亡くなったペットとの絆をずっと大切にし続けている背景として、人間同士の絆が薄くなっている点なのである。
古代から、人類文化では死者を葬ることは重要な意味をもっていた。追悼、弔いというのは、一人ひとりの心の中の問題であると共に、社会の共通の問題でもある。それは生き残ったものがどのようにその死者の存在の意味を認め、どのような未来を育てていくのかということと、弔いが繋がっているからなのだと思う��。
ことに親子、夫婦、兄弟の死は辛いものであるから、人類文化はそこから立ち直る心の修復のために多大なエネルギーを費やしてさまざまな儀式や行事を行ってきたし、慰霊・追悼の文芸や音楽や美術品も少なくない。だからこそ、いま安易にデジタル技術を用いて、その傷を埋めようという発想には危うさを感じる。